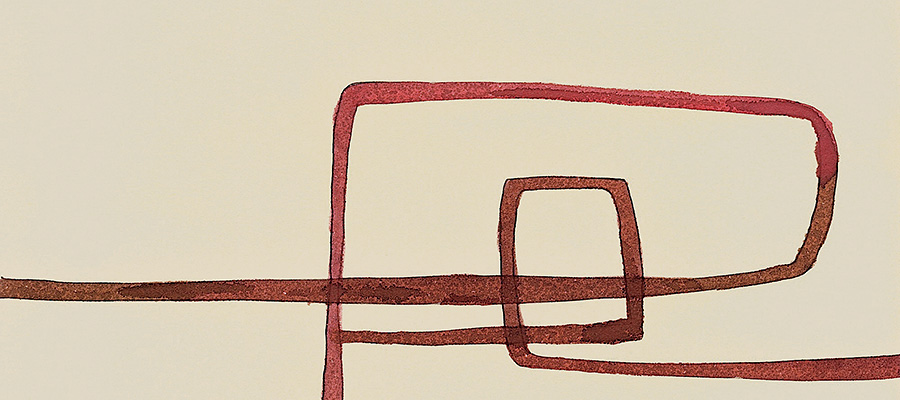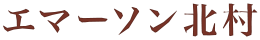<中心地区を歩く>

この旅行記にも何度か出てきたCBDとはセントラル・ビジネス・ディストリクトの略で、政府機関や企業本社が集まる、文字通りナイロビの中心となる一角を指している。ここと、道一本隔てたダウンタウンとを合わせたエリアが、多分ナイロビで唯一、徒歩で都会らしさを感じることのできる地域だ。僕にとってはまず最初に歩いてみたいところだったが、MariさんOtiさんご夫妻はあまり積極的でない。やはり危険という理由から(いわゆる犯罪だけでなく、写真をとっていると官憲からとがめられ、金を要求されたり拘束されそうになることもあるらしい)だが、実際にどうかということはさておき、長年街の変化を目の当たりにしてきたご夫婦にとって、治安を含めてすっかり変わってしまった市中心部は、もはや足の向く場所ではないのだろう。その気持ちは、僕にもよく理解できた。

とはいえやはり一度はCBDを観ておかなくちゃ、ということで、例のアーティストトークまでの「待機期間中」のある日、三人で出かけてみた。
やはり来てみて良かった!CBDのそのまた中心にある郵便局や銀行本社など、独立前の建築と思われる古くてモダンなビル群。そしてビジネスマンから物売りまで、街角に居る大勢の人びと!ナイロビの他地域では見ない、ビシッとしたスーツで歩いている老人などもいて、とてもかっこいい。
続いて、旅行者には危険と言われるダウンタウンへ向かう。ところが、道を一本渡るだけであっけなくそのエリアに入ってしまい、「あれ、もうダウンタウンなの?」と思うくらい、風景はCBDと変わらなかった。…と思っていたら、最初に気づいた変化があった。
それは、音。車の音や人の声が高くなり、まるで騒音の隙間をぬって風景を見ているようだ。携帯屋、レストラン、通りの先にはイスラム風の建物も見える。市場のようだ。そしてダウンタウンの目抜き通りには思い思いのペイントを施したバスがズラリと停まっており、バスの前に立ったおっちゃんらが道行く人々に何やらアピールしている。ここは長距離バスの発着場所なのだ。
ケニアでバスは個人営業に近い形で運行されているらしく、車掌と客引き?を兼ねたおっちゃんらが「ウチのバスへどうぞ」と競う様子は、有名なのだそうだ。かつてはファッションリーダーの役割も果たしていたらしい(プランドものでキメた、90年代リンガラバンドの衣装に通じる発想だ)。そうした「客引き芸」のひとつなのか、おっちゃんらの鳴らす口笛?のテクが半端ない。唇ではなく歯か何かを使っているのかもしれないが、口をすぼめて出すリズミカルな音の大きいこと!何人ものおっちゃんが競って吹くその口笛が、重なっては街の騒音と同期して、確実にひとつのグルーヴを作っていた。写真が撮れなかったことより、これを録音できなかったことの方が悔やまれる。

Nairobi Odeon と書かれたかつての映画館(ネットで調べたところでは1950年代に建てられたらしい)を横目で見ながら短時間のダウンタウン歩きを終え、再びビジネス街へ。
ナイロビのランドマークであるケニヤッタ国際会議場へは一応押さえおくか程度の気持ちで向かったのだが、行ってみるとこれがまた僕の古ビルマニア心に訴える素晴らしいものだった。1970年代にヨーロッパ人の設計によって作られた建物はとても良く整備されていて、まるで当時の映画のよう。おまけに28階の屋上(戸外!)に登ることができるという。ビルだけでなく高いところも大好きな僕は、即決で展望エレベータのチケットを買った。

さっき歩いたダウンタウンがビルの間から見えている。ナイロビ駅のレンガ造りのヤード。日本大使館のあるアッパーヒル。どのエリアが何を目的とする地域なのか、一目瞭然に配置されていて昔のゲーム「シムシティ」の画面のようだ。中心部から少し離れると緑が増え、真新しいオフィスビルが建つ。クオナやレコーディングをしたスタジオは、そのあたりだ。遠くには、ンゴングヒルも見える。車で走り回っては、演奏したり楽器を運んだり人に会ったり買い物したり、そしてつい10分前までその喧騒にもみくちゃにされていた街が、指先でつまめるようなサイズで並んでいる。爽快な風景なのにちょっと寂しいような、何とも言えない気持ちになった。

ナイロビの街について、もう一つ書いておかなければならないことがある。それは「スラム」の存在だ。最大の「スラム」であるキベラ地区は、ショッピングモールの並ぶキリマニ地区の隣、幹線道路を超えてすぐのところにある。今現在も、水の調達にさえ苦労するような生活がそこにある。キベラで孤児やストリートチルドレンのための学校を運営している早川千晶さんからはそこでのライブのお誘いをいただいたのだが、スケジュールが合わず実現しなかったのは残念だった。幹線道路に入るジャンクションを通るたびに、建ち並ぶマンション越しにキベラが見えていた。キベラだけでなく、市内を走っていて「あれ、ちょっと雰囲気変わったな」と思うと、トタン屋根の家並みがすぐに現れる。高級マンションが増える一方でこういう生活はなくならない。そして日本からライブをしに来て、それを高いところからも低いところからも眺めている僕がいる。自分は一体、どこに属しているのだろうか?

<アーティストトーク>

3月8日金曜日、ついに Kuona Artists Collective において「Emerson Kitamura Artist Talk」が行われた。外国人の、しかも美術家でない人がトークをするのは相当珍しいとのこと。敷地の中庭にキーボードと椅子を出して、20人ほどが集まってくれた。ほとんどはここで制作活動をしている美術家だ。

テーマは、How African music inspired my music? アフリカの人々を前に一度自分のアフリカ音楽に対する理解を話して、それが伝わるのかどうか試してみたかったのだ。内容についてはまた改めてレジュメをアップしたいと思うが、自分が話したこととその反応を、簡単にまとめておく。

(1)まず僕が誰で何をしにナイロビに来ているか自己紹介したあと、自分の音楽はアフリカ音楽にインスパイアされてきたことを話す。
そして、日本のポピュラー音楽は欧米だけでなく非欧米の音楽に対してもオープンになった時代があったことを、実際の音楽をかけて知ってもらう。それがどう聴こえるか、アフリカ音楽の影響があると感じられるのかどうかも、教えてほしい。
時間がなくて二曲しかかけられなかったが、一曲目は:
トニー谷「チャンバラ・マンボ」。参加者は、みんな笑っていた。ラテンと講談のミックスは、よく伝わっていたようだ。
二曲目は:
暗黒大陸じゃがたら「クニナマシェ」。個人的にもぜひアフリカの街で、アフリカの人の前でじゃがたらをかけてみたかったのだ。この音楽は何に聴こえますか?「Hip Hop」「Funky」との答えで、アフリカ音楽という答えはなし。
(2)アフリカの音楽の構造について、僕が思っていることを、キーボードを弾きながら話す。リフがとても機能的にできていること、十六分音符のすべてのタイミングが公平に絡み合ってグルーブを生み出すことなど。ちょっと専門的すぎて、美術家には伝わりずらかったかも知れない。
(3)各パートが別々のことをやりながら全体としてひとつのグルーヴを作り出すのがアフリカ音楽やレゲエの特徴だということ。その典型的な例として「ベースライン」の話をする。ベンガでも特徴的だったベースライン。そこから話はレゲエにそれて、「ベースラインだけ聴くと何の曲だか全然わからない超有名曲」クイズを出す。これはMUTE BEATのベーシスト松永孝義さんが生前やっていた「持ちネタ」を拝借したもので、会話で盛り上がらなかった時の保険として用意していたものだ。予想通り、トークより演奏の方が盛り上がる。アンコールまでもらって、結局トークだかミニライブだかわからない感じになって終了。曲は One Loveでした。
(4)質疑応答。「アフリカ音楽を聴いた時、歌詞についてはどうでしたか?」という質問に、全く答えられず。ここでもまた第5回に書いた問題につきあたる。「歌詞は意味だけでなく音でも伝わることがある」と言いたかったが、上手く英語で言えず、しどろもどろになると「でも言葉のバリアを壊してゆくのは良いことだわ」と逆にフォローされる。

英語は下手だが、翻訳した原稿を読み上げるだけではさらに伝わらないと思ったので出たとこ勝負の英語で話したが、思ったより単語が出てこなく、やはり簡単な翻訳の準備はするべきだった。しかし下手でも、日本語から翻訳せずに話しているときの英語の方が自然に話せているという、見ている人からの指摘もあった。クオナのメンバーからも「良いプレゼンテーションだった」との感想をいただき、ホッとした。

<アフリカ・ヌーヴォー>

午後にアーティストトークが終わって、この日にはもうひとつやりたいことがあった。クオナで見かけたフライヤで知った、今回がまだ2回目というピカピカに新しいケニアの音楽フェス、Africa Nouveau http://africanouveau.com/ を観に行くのだ。
会場は市の西郊の競馬場。植民地時代のイギリス文化で競馬場は上流の人々が集う場所であったためか、静かな池と芝生とが非常に美しい。そこにステージやDJブース、出店のテントが並ぶ。アフリカ美術の展示にも力を入れていることと、飲食店のスタッフが会場内を回って注文をとる(ちょっとうるさい)ことを除けば、完全に日本のフェスと同じスタイルだ。ケニアで目にした風景の中で一番なじみのあったのが、おそらく欧米を参考にしたであろうフェスの風景とは何か皮肉だなと、昨夜の真っ暗なベンガ定食屋を思い出しながら、ナイロビで始めてのエールを飲む。集まっている人々はおしゃれで、初日のSupersonicスタジオで見て以来の「イケてる」人々であることは明らかだ。でも日本のような、ただお金があるだけの富裕層とは何かが違っているのも感じた。例えば、たまたまこの日が重なった国際女性デーのことがMCで取り上げられていたり、話してみてもコミュニケーションが前向きで、素直にいい感じなのだ。一緒にフェスに行ったMariさんは「ナイロビでこんなフェスが実現するなんて、なんだかしみじみしちゃう」とおっしゃっていた。組織だったイベントができたという以上に、そこに集う人々の雰囲気が、そんな感じを与えたのではないかな。

夕暮れのフェス会場で、今までに見たナイロビの風景を思い出しながら、ここにある格差のことを考える。
ナイロビにいてたくさんの人から「昔は良かった」という言葉を聞いた。昔はもっと治安が良かった、昔はバスが時刻通りに走ってた、昔はもっと面白い音楽があった、などなど。もちろん経済発展の恩恵は一部の人だけでなく、薄い形では多くの人の生活に便利さをもたらしていると思う。それ込みでの「昔は良かった」だと思うのだが、キベラに代表されるように、格差は縮まるどころか拡がるばかりだということもまた人々に、はっきり認識されている(ライブ2ヶ月前の2019年1月には、高級ホテルの入る施設がアルシャバブに襲撃された)。
そんなナイロビの姿をもはや「日本とは違って」と表現することはできないだろう。「発展/途上」という区分けで我彼を比べることは、もはや全く意味がなくなってしまったからだ。しかし同時に、「経済発展に伴う矛盾」とひとことで片づけるだけでは、そこから抜け落ちる暮らしがたくさんあることもまた確かだなと思った。
暗い食堂ですごい演奏をバックに無表情でご飯を食べる人々、街角で何やら大声で主張し合っている人々、ノーと言わないまま物事を進めたり進めなかったりする人々、フェスでハグし合っている人々、そして夕刻の坂道を歩く通勤帰りの人々。その全員が、それぞれのリアルな時間を生きている。僕がナイロビでわかったことは、それだけしかない。

← (6)ついに生バンドに遭遇 へ