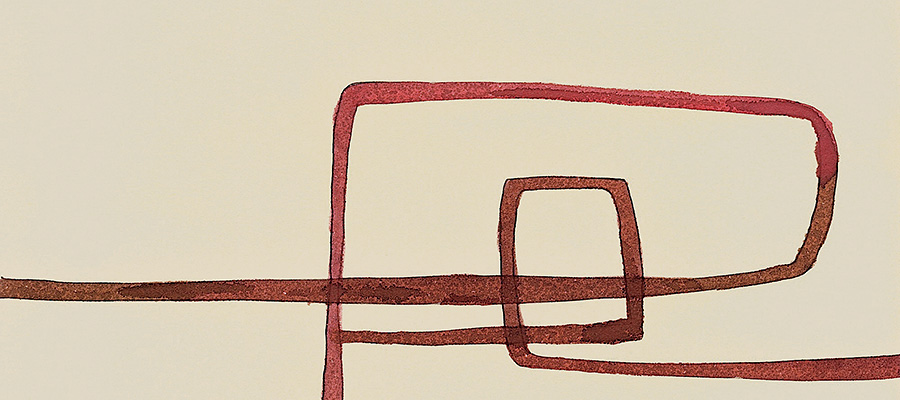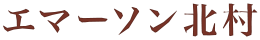このアルバムの前年2018年に、mmm with エマーソンはカセットテープをリリースしている。すべてオリジナルからなる4曲入りで、うち3曲はCHASING GIANTSにも収録されている。ライブ会場限定での販売だった(現在は通販もしています)。EU・UKツアーが決まって音源を作ることにした当初は、この4曲を中心に何曲か加えればそれでアルバムになるだろうと思っていた。しかしある時点から、これから作ろうとしているものは、カセットとは曲数だけでなく質的にもまったく違ったものになるだろうという気がしてきた。そう思い始めたのは、2019年の春にmmmからこの曲、Chasing Giantsのデモを聴かせてもらった時だった。

デモ時点でmmmの歌詞とメロディはほぼ完成していた。「今のところ、私の日常は、まあ静かなもの」という冒頭から始まって、「そしてそれから、繰り返す(一番にはなくて、二番に出てくる)」という言葉を合図にとめどもなく逸脱してゆく思考。僕は特に、「生命のないものが鮮やかな色に取り込まれてゆく」という部分の歌や、「一日中円を描いている」ような孤独感、そして軽く言えることではないが、エウリュディケを連れて冥界を歩く神話のワンシーンが、「死んだ妻の話」として後の「夏至」にも通じるモチーフを持っていることなどに、深い印象を受けた(歌詞は対訳でなく、北村のイメージ)。

ところがmmmは、この曲には納得できない部分があるからボツにしたいと言う。大あわてで理由を聞くと、自分の歌っている音が小節の拍の中でどこにあるのか分からないから、ということだった。この曲は6拍子なのだが、同時に2拍子とも3拍子とも4拍子とも「取る」ことができる。どのように拍を「取る」かは楽器を演奏するためには大事な要素だが、ジョン・レノンの曲に自然な変拍子が多いように、歌を歌う分にはそれほど気にしなくても済む。しかしそれを納得いかないと感じるmmmは、歌い手であると同時にミュージシャンとしての資質も大きいのだろう。これもデモ段階ですでに完成していたギターのリフというかベースラインと自分の歌とを、音楽の共通言語の中に落とし込めないことは、その曲をボツにしかねないほど大きな問題だったのだ。

それで、僕の役割は決まった。「ただ数えること」。
すべてのフレーズが「いち、に、さん、し、ご、ろく」を明確に示しながら歌と共に進んでゆく、そんな演奏をすること。

「ただ数える」というのは単に技術的に正しく演奏するとか、歌を「立てる」ように演奏するということではない。歌い手の表現するメロディに対して、それが「どこにあるのか」を示す座標軸、遠近法の絵ならば消失点に向かって引かれる直線のようなものだと思っている。それはメロディと同じくらいエモーショナルで、「気合」を必要とする作業だ。
「どこ」にはいろんな意味がある。拍やコードといった理論上の意味はもちろん、アイデアが古今の音楽スタイルのどこに位置するかということでもあるし、もっと個人的な、自分の感情の中でどんな場所を占めているかという問題でもある。そのどれか一つでなく、すべてがうまくバランスを取れた時、曲は人に伝わるものになる。だから共演者にも、知識やアイデアだけでなく、それが自分の「どこ」にあるのかをはっきりとらえることのできる力が必要とされる。
何もない無音の空間に最初の音を置くことは、何度やってもおそろしい。「いち」の次に「に」をどこに置くか、「さん」までどのくらいの距離があるのか、一音ごとに問われる中で余計な「意図」などにとらわれず演奏を歌い手に示してゆくことが、「ただ数える」ということである。

そんなわけでこの曲は、どちらがギターだかキーボードだか分からないユニゾンから始まって、手作業のループが加わり、ダイナミックなパートから間奏へと拡がる展開を通じて、あえて言えばどこにも僕「独自」のアイデアはない。ひたすら歌詞と一緒になって、どこへ向かうのか分からない心の中を、mmmとは別の時間軸上で「ただ数えながら」展開させているだけなのだ。そして、曲自体もどこにたどり着くのか見えないかのように、歌は繰り返し、パートの間を行き来する。この「繰り返す」ということもCHASING GIANTSの大きな要素だと思うが、それはまた別の機会に書いてみたい。

もうひとり「ただ数えている」人がいる。ゲストドラマーである菅沼雄太(僕はEGO-WRAPPIN’のサポートを一緒にした時の癖で「すがちゃん」と呼んでしまうので、以下すがちゃん)だ。
mmm with エマーソンは主にサンプラーシーケンサーを使ってドラムの音を出しているが、特にそれを理想としているわけではない。しかしまた、一度ドラマーに演奏してもらったら、それが良い結果であるほど「あと戻りはできなくなる」ことも分かっていたから、アルバムに生演奏を加えるべきか、僕は迷っていた。しかしこの曲の準備が進むにつれて、そろそろ「潮時」かなと思った。人選は悩まなかった。mmmも坂本慎太郎バンドですがちゃんの演奏は知っていたから、話は早かった。あとは、演奏の希望をどう伝えるか。

冒頭のハイハットに対する僕のイメージはずばり、これだった。
João Gilberto / João Gilberto (三月の水)1973
フルセットで入ってからのドラムには特にお手本はないが、僕は基本、パンキッシュかつグルーヴのあるドラムが好きだから、その王道を行ってくれると信じていた。あえて僕が理想とするドラマーを挙げるなら、Ian Dury and the Blockheadsのドラマー、Charlie Charlesがそのナンバーワンだ。
New Boots And Panties!! / Ian Dury 1977
我々の希望を彼らしいフィルターに通して、すがちゃんはアルバムで聴ける通りの丁寧な演奏をしてくれた。嬉しい。

レコーディングの音色音質については僕は意外とこだわりがなく、「演奏したままが録れればいい」と思っている。しかし「演奏したまま」の音ほど難しいものはないのもまた事実で、今回のレコーディングでも、スタジオから家に帰ってプレイバックを聴いてみると少し思い違いがあったので、細かな修正作業をした。専門用語で申し訳ないが、ミリ秒単位でも位相が変わるとタイム感が違って聴こえるので、それを演奏した印象の通りに戻したかったのだ。ドラムが決まらなければミックスは進まないので、5分間の演奏に一週間近い日々を費やした。さすがにこの時は、アルバムが出ないんじゃないかと周りに危ない思いをさせた。

ベーシックが録音できてから、ホーンを加えたいとアイデアを出したのはmmmだ。フルートとフリューゲルホーン、二菅のアレンジ(和声を考えること)を書いたのも彼女だ。僕がしたことは譜面をきれいに書き直したことと、誰に頼むかを考えたことだけ。この曲には、Jazzyになりすぎず、また和声だけでなく演奏のグルーヴも分かってくれる人が必要だと思ったので、icchie に頼んだ。icchie はYOSSY LITTLE NOISE WEAVERでエマソロのかなり初期からイベントを一緒にやったり、トラックメイカーとして自分のレゲエ作品も作っている、信頼のおけるミュージシャンだ。2020年2月のリリースライブではワンホーンで参加してもらったが(mmmは歌とフルートを同時にできないから)、ハモりがなくても大きな拡がりを生んでいたのには驚いた。

ほとんどの要素がデモの中に「隠れていた」ものを見つけ出す作業だったのに対して、唯一そこにはない、それまでのステディな流れをぶち壊すようなギターソロのアイデアも、またmmmによるものだ。鉄の棒でエレキギターの弦を叩いて音を作っている。ライブでもこの「ナイスな棒」を使おうとしたが、ソロの瞬間に棒に持ち替える良い方法が見つからないまま、今に至っている。

Giants といえば当然、ジャケット画の「巨人」やTシャツのイラストにも触れたいのだが、分量が増えすぎるので、これもまたの機会にさせてください。