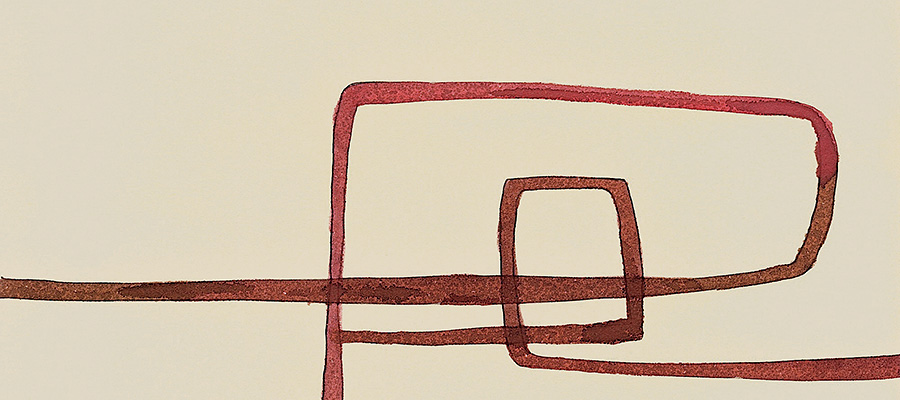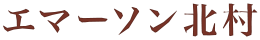海外で評価され、ヨーロッパツアーのきっかけともなったRock Your Babyに次ぐ「グルーヴもの」の新曲。しかし単なる「次」ではなく、Rock Your Babyよりもはるかに込み入って、それぞれの「妄想」が十分に現れる曲になった。そのわけのひとつにはmmmの歌詞、もうひとつには僕の、レゲエを要素として音楽を作る上でのこだわりがある。

レゲエでは、トラックが歌から独立していて、ひとつのトラックにいろんな歌が乗るのは普通のことだ。レゲエ(というか、その元となった1960年代末のジャマイカ音楽ロックステディ)を少し聴いたことのある人なら、この曲のトラックがいつのどの曲に影響を受けているかを簡単に言い当てることができるだろう。それはそれで面白いことだが、僕のこだわりはそういった「音楽スタイル上の正しさ」にはない。普通は「別々」のものである歌とトラックが、一緒になってできあがるような曲にすること、そして、ロックステディから逸脱しながら、ちゃんとそこに戻ってくる曲にすることが、僕の目標だった。それはロックステディという音楽自体が、始めからそういうものだからだ。

以前から僕は、カエターノ・ヴェローゾのアルバムTransaに入っているNine Out of Tenという曲の雰囲気で何か作れないかと思っていた。カエターノのロンドン亡命中に作られ、「ポートベローを歩いていたら、レゲエが聴こえてきた」と英語で歌われる曲(例によって訳は対訳ではなく北村の想像訳)。その心情は一曲前のYou Don’t Know Meという曲のタイトルにも表れていて、曲そのものはレゲエでないことがまた良かった(イントロで一瞬だけレゲエでも演奏されている。この部分のコード進行は「夏至」のサビに影響を与えている)。そんなことを思いながら、この曲が作られた1970年代初頭に聴こえるレゲエと言えばルーツレゲエではなくロックステディ、ロックステディと言えばジャッキー・ミットゥーのDrum Song、という連想で「夏至」のベースラインができていった。(正確にはDrum Songは1968年で、カエターノが聴いたであろう初期レゲエよりも少し古い。時代考証を何より大事にする方には申し訳ないけど、僕はあくまで音で思考しているのでその辺は意外といい加減だ。)

ベースラインが見えたところで次に、メロディや構成は、他の共作曲とは違って二人でジャムしながら作りたいと思った。例えば街のあいだのような曲は、各々が相手の提案をファイルで受け取ってから、一人でアイデアを重ねるという方法で作られた。実は僕は、バンドで延々ジャムしながら曲を作るのは、あまり好きでない。よっぽど気心の知れたバンドならともかく、「グルーヴに委ねて」と言いながら実は相手の出方をうかがっているだけという「ジャム」の多さに、ちょっと飽きているのだ。ファイルのやりとりの方が、リアルよりももっと相手との距離を縮められる場合の方が実は多い。しかしこの曲では、歌がなく、ソロもなく、ただ「グルーヴに委ねて」いるだけの時間を作りたいと思ったのだ。

ジャムすることで予想通り?曲はどんどん普通のロックステディから逸脱していった。キーは短3度で上がったり下がったり、リズムはスローファンキーとワンドロップを行ったりきたり。極め付けは我々が「心中」と呼んでいたパートで、ここは何だろう、ニューウエーブ?しかしこのパートのおかげで曲は意味あるものになった。それを支えているのは、mmmの歌詞だ。

歌詞を書いてもらう前に、僕は彼女にこんな話をした。僕はレゲエが好きだけど、古いレゲエに多い、マッチョで男性優位的な内容の歌詞にはついていけない。歌詞だけはレゲエにはないものにしてほしい。そうしたら彼女は、まさかの幽霊譚、同時にラブソングでもあるような幽霊譚を書いてきた。どうも彼女は、僕のひねったリクエストに対しては、さらにもうひとひねり加えて返してやろうと狙っているようだ。そんなあまのじゃくは、大歓迎だ。

演奏上の特徴はもちろん菅沼雄太(すがちゃん)の参加、そして何と言ってもmmmのベースとフルートだ。mmmはもちろんレゲエベースは初めてと言っていたが、むしろ中途半端に「レゲエベースとは」などど考えていない演奏が、良いグルーヴをもたらしている。だってジャマイカのミュージシャンは「レゲエっぽくベースを弾こう」とは言わないでしょう?ただ良いベースを弾きたいと思って演奏する、それと一緒なのだ。すがちゃんは口径のとても大きなバスドラムを持ってきた。それがさほどローエンドのないもので、良かった。大きなバスドラムは低音がたくさん出るというのも、レゲエはローエンドを強調するということも、実は間違った常識。

ミックス上の特徴は、この曲ではダブっぽい要素もあるのに、ディレイをほとんど使っていないことだと思う(「心中」パートでは使っている)。mmmのフルート、すがちゃん、そしてエマーソンと、人間の側ですでに「ダブ」ができていると思ったからでもあるし、僕が最も好きなダブアルバムTreasure Isle Dubの、ほとんどディレイが使われていないミックスも念頭にあったからだ。

ロックステディの話に戻る。ロックステディを担ったミュージシャン達はこの時期に、驚くほど幅広い音楽を取り入れている。インプレッションズをはじめとするUSのコーラスグループはもちろんのこと、モータウン、ファンキー、オルガンジャズ、はてはイージーリスニングやエキゾチカといった「白人音楽」まで。僕がレゲエ、特にロックステディを好きで良かったと思うことのひとつは「レゲエの中にすべての音楽が入っているし、すべての音楽の中にレゲエが入っている」と感じられることなのだが、その理由は、自分たちだけのものである太いグルーヴ(ベースライン、3拍目の重要さ、コピペでは作れないループ感など)は、外からの要素が加わってもまったく薄れることがないからだ。ロックステディに影響を受けて音楽をやるということは「それっぽく」演奏することではなく、はずせない部分は押さえながらも、進んで逸脱して、形式ではないその曲の持つストーリーに常に戻ってくることだと思っている。

この曲のストーリーは、「月に透けている、嫁に行ったはずの娘」に集約されている。彼女の中には、カエターノが1972年に「お前らみんな、俺のことなんかぜんぜん知らないだろ」と歌った気持ちに通じる「見えていない寂しさ」が流れている。

ロックステディは本当に不思議な音楽で、それが制作されたのはスカとレゲエの間に位置する、1966年から69年くらいまでの、たった3年ほどの間だ。その間に作られたレコードを、30年や40年かけて集め、聴く人が大勢いる。音楽の流れにおける時間の不均等さ、「伸び縮み」はこんなところにも現れている。