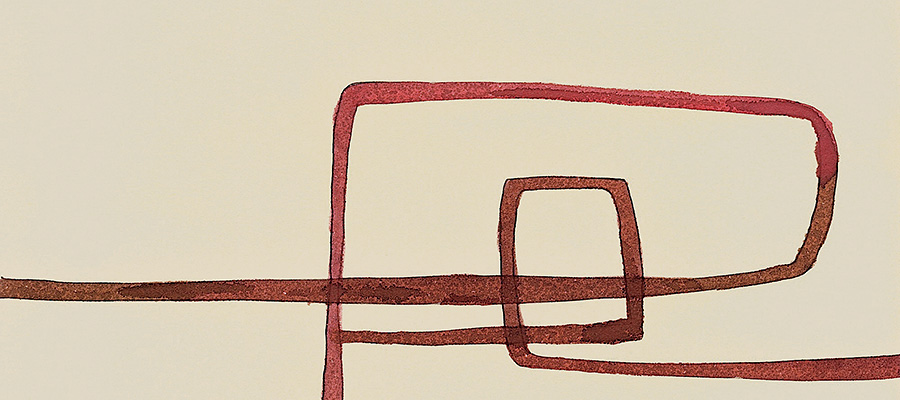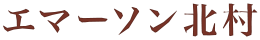キーボードプレイヤーが一度に使う楽器の物量は以前に比べてすいぶん減った。電車の中などで、ギタリストと同じような姿でキーボードを背負っている高校生などを見かけると、なるほどと思う一方、自分がかつて「キーボード・マガジン」などで楽器の軽量化を主張したにもかかわらず、なんだか彼らの負担で効率化だけが進んでいるような感じもして、「本当にこれで良かったのかな」ともちょっと思ってしまう。
とはいえ、ライブの場などで何台かのキーボードを使い分けるケースは今でも多い。曲中で音色の違うパートを弾き分けるには、その分の数の鍵盤を揃えることがいちばん分かりやすいからだ。その場合、僕は「使われる何台かの楽器が、全体としてひとつの楽器として聴こえる」ように、注意してバランスをコントロールしている。これはキーボード奏者の中では特殊な方かもしれなくて、多くの人は、鍵盤のひとつひとつを良いバランスで弾くことには気をつけるけど、各々の楽器のバンド全体におけるバランスはそれを整えるべき人におまかせ、というやり方をとっているようだ(いや、よく分からない。こんな重要ことが、ミュージシャンという者には意外とわからない)。
僕が複数の楽器を全体でひとつの楽器ととらえる理由はいくつかあって、すべてのキーボードが別々のバランスを取ることですべての場面ではっきり聴こえるようになるよりも、一人の演奏する楽器群としてダイナミクスが一つにまとまることで、他の奏者の演奏と一緒になった時に、聴こえる時は聴こえ、埋もれる時は埋もれるようになった方が、バンド(のその日のショウ)全体のダイナミクスがより「リアル」になるのではと考えているのがその第一なのだけど、もっと背景的なことを言えば、僕がキーボード奏者として、ピアノではなくオルガン(電子オルガン)をルーツに持っていることがあると思う。
オルガンは、鍵盤が三段揃った状態が正式で、それぞれアッパー/ロワー/ペダルと呼ばれる。ペダルはいわゆる足鍵盤。なぜピアノは一段なのにオルガンは三段も必要なのかというと、オルガンは鍵盤を押さえただけでは音量も音色も変化がないので、例えばピアノではコードとメロディを同時に弾くときはタッチの変化でそれぞれに合った音量音色を表現するけど、オルガンではあらかじめメロディ用とコード用に作った音色を別々の鍵盤に振り分けておくことでしかそのバランスを表現できないから。それぞれの音色はオルガンの内部でひとつにまとめられてスピーカーなどに送られる。鍵盤がいくつあってもそれらは一つの楽器としてダイナミクスをコントロールするために使われる。これがオルガンの考え方で、その考え方を数台のキーボードに対しても拡げたのが、僕の発想のもとになっている。このことはあまり指摘されたことはないのだけど、唯一、UKのマンチェスターで mmm with エマーソンのライブを行った時、お客さんから「あなたのキーボードプレイはシンセを使っているけど、オルガンが基本ですよね」と正しく指摘された。さすがマンチェスター、音楽わかってる。
そんなわけで、僕は足鍵盤も普通に弾く。よく「足で鍵盤なんてすごいですねー」と言っていただくのだけど、僕にとっては自転車に乗るような感覚で、すごいことをやっている感じはない。ただよく誤解されるのだけど、足鍵盤は「ベース」とは違う。たぶんこの誤解はいわゆるオルガンジャズ、ベーシストがおらずオルガン奏者が低音の4ビートを弾きながらアドリブもする音楽をレコードで聴くことから始まったと思うのだけど、実はあれば足でなく、左手で弾いている場合がほとんどだ。ポピュラー音楽のオルガンにおいて足鍵盤が多く使われるのはそのような場面ではなく、例えば米国の野球場やスケート場で演奏されるようなイメージの、フルバンドを雇う余裕のないBGMとか、あるいはなんていうか、ちょっと演芸の雰囲気を伴った演奏(ほら、こんなにたくさんの鍵盤を弾いとります。足も使ってます!)など、「純粋じゃない音楽」の雰囲気がある。そしてそういう音楽、僕は結構嫌いじゃない。
そんな欧米のオルガン軽音楽における足鍵盤が「ベース」の代わりであると思われるようになったもう一つの理由は、日本独自のものである、電子オルガン教室にあると思う。僕も通ってました。足鍵盤をベース、下鍵盤をコードバッキング、上鍵盤をメロディとそれぞれバンドアレンジのパートに対応させる発想は、はっきりと「エレクトーン教室」のものだ。「エマソロ」のスタイルはある意味、そこで習ったことを教室の外の音楽へありえないほど拡げた結果であり、素直も度をこせば変わったものになってしまうということの見本なのかもしれない。(脱線ついでに、子供の時の少し恥ずかしい思い出でしかなかったヤマハ音楽教室については、音楽史・産業史の観点から客観的な研究がされているということを最近知って、「外からの」音楽の受容の過程という意味で自分の中に改めて置き場所ができる感じがした。いずれまた詳しく)
足鍵盤を弾いていて唯一難しいのは、レゲエのベースラインのような早いフレーズが弾けないことだ(当たり前だ)。そして自分にとってベースの動きというのは、アレンジの中で最も大事なものだ。COVERS 2003のレゲエ曲では、足鍵盤は「省略ヴァージョン」のベースラインを弾いていて、その残念さが以降のエマソロではベースラインを左手で弾くスタイルを増やした理由となった。しかしそうするとレコーディングではダビングを多用せざるを得ず、COVERS 2003のようなライブ録音(ライブショウではなく、いわゆる一発録りのこと)のシンプルさは減ってくる。ここがエマソロの悩みどころで、今でも解決法を誰かに教えてほしいと思っている。