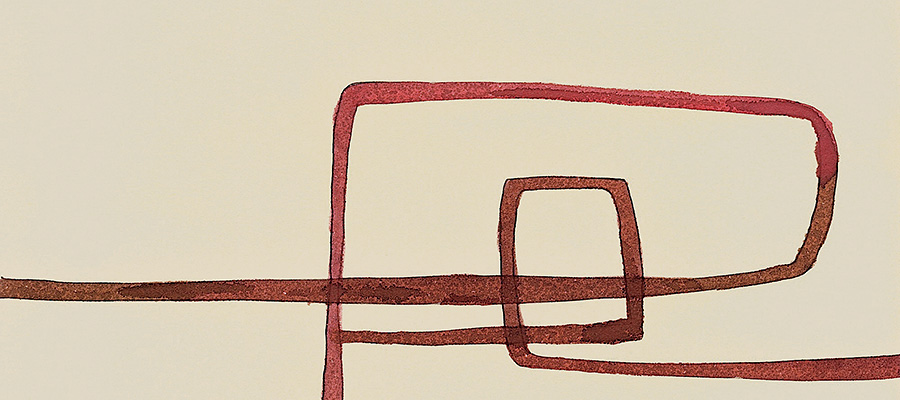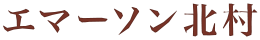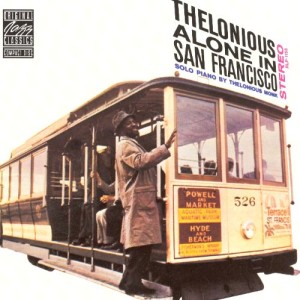「ロックンロールのはじまりは」のラストトラック「中二階」の話です。
「ロックンロールのはじまりは」のブックレットに収録されている文章の中で最も触れられて「いない」のが、スカやロックステディ、レゲエについてだ。歴史的な順序としては、アメリカではロックンロールを生んだジャンプ・ジャズやリズム・アンド・プルースといったその同じ音楽がジャマイカではスカを生んだわけだから、それは「ロックンロール」ではあっても「はじまり」とは言えないので、なかなか話に登場しなかったのだ。
しかし、やはり僕が一番好きなのは「スカやレゲエのはじまりは」というべき音楽で、数年前に出た『The Story of Blue Beat』というコンピレーションはよく聴いたし、「遠近(おちこち)に」発売後のツアーの車中で一番聴いていたのは『The Trojan Story』という、ジャマイカンR&Bからロックステディに至る、基本中の基本みたいな盤だった。大体、僕は仕事に終わりが見えてくるとブルース進行の曲が作りたくなってくる癖があるようで、1993年に作ったカバーソロアルバム(トラックは他の人に作ってもらっているからエマソロとは呼べないかもしれない)でも最後の曲は「Blue Gold」というブルース進行のオルガンものだった(廃盤)。
そんなわけでこの曲は「遠近(おちこち)に」ツアーの末期に原案ができていて、最終地の京都・磔磔では今とは別物だけど、原型となる曲をライブで演奏したりもした。ジョージー・フェイムの『Rhythm and Blue-Beat』のように、裏打ちのパートもピアノではなくオルガンでやってしまうようなサウンド。そんな基本のロッキン・オルガンに対してトラックはデニス・ボーヴェル’81年のソロアルバム『Brain Damage』収録「Run Away」のような、硬い硬い音色でシャッフルスカをやっている、というサウンドにしたかった。そして、エマソロには珍しく(?)仕上がりもその通りのサウンドになっている。
「中二階」というタイトルについて。そのツアーで盛岡に行く時、たまたま、普段より少しだけ高めのホテルがバーゲンになっていたので、嬉々として予約した。実際、古い建物だがきちんと手入れされた良いホテルだった。日曜の朝にお茶を飲んだそのラウンジは、石を貼った階段の先が中二階になっていて、差し込む光と少し厚着をした人達の集う様子が、何か、とても良かった。「遠近(おちこち)に」にも「10時の手帖」という、石造りの踊り場をイメージした曲があって、ミックス的には「石→反響→リバーブ」という連想が働くサウンドでもある。
なぜか僕は中二階に「弱い」。光線の加減もあってか、石で作られていても柔らかな、何かとても「生々しい」ものを感じるのだ。そして僕の想像は、敗戦直後の建築に関する本で見た、ある書店の中二階の写真に飛ぶ。バラックのような建物にあって、その中二階には光が満ちていて、苦労して入荷された本を求める人達が集まっていた。中二階だから感じられる、その生々しさ。それは「ロックンロールのはじまり」に対応するイメージなのだ…その先はCD「ロックンロールのはじまりは」のブックレットに書いた僕の文章につながるので、ぜひ盤を買って読んでいただけたらと思います。
6曲分のセルフプレビュー、読んでくれてありがとうございました!
そのホテルのエレベータ