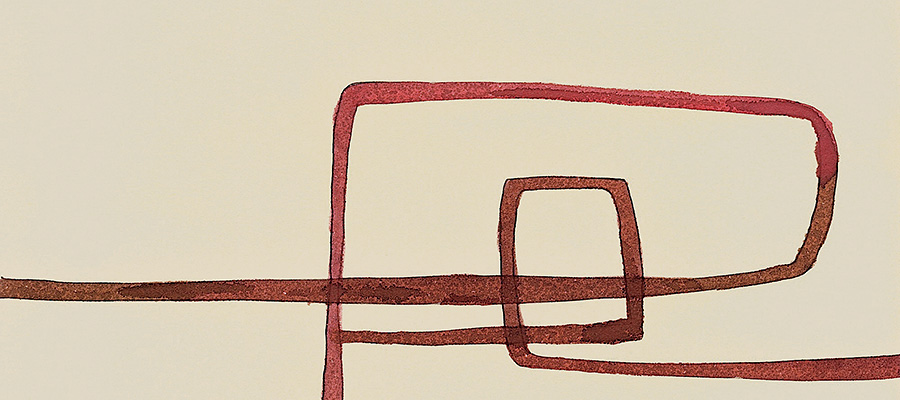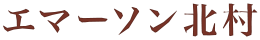先日、敦賀でのエマソロイベントで、COVERS 2003 の発売以来、最もハラハラする瞬間があった。
地元のDJチームの方が、二十年前から持っていたオリジナルの7インチと購入されたばかりの COVERS 2003 とを二台のターンテーブルに乗せて、その音質を聴き比べるという場面に出くわしたのだ。まさにこんな機会もあろうかと、この夏はカッティングエンジニアさんと何度もやりとりしてきたのだ、とひそかに思いながら、一方で、再発の方が音が悪かったらどうしようと不安でもあった。結果は、思ったとおりでもあり、意外でもあり……でもマスタリングされた作品の音というのはそれで良くて、むしろ「思った通り」だけではつまらないと考えている。そのことはこの欄の最後に書きたい。とにかく yoiyoi クルーの皆様、ありがとうございました!
COVERS 2003 のマスタリングを行うにあたって、最近ではすっかりやらなくなった作業から始めることになった。マスターテープを探すことだ。ハードディスクではなく物理的に家の中でものを探すという行動自体が久しぶりだった。そして、当時の DAT テープを発見した(写真)。見たことのない人も多いと思う。カセットテープの7割くらいの大きさで、テープだけどデジタルデータを記録している。
しかし結局、このテープを今回の元音源とすることはできなかった。家にもカッティングをお願いした工場にも、DAT を安全に再生できるプレイヤーがなかったのだ。再生できないというよりも、テープが機械の内部で絡まって切れてしまうような危険性を考えると、テープをかけること自体が一種の賭けになってしまうからだ。結局、このテープをハードディスクにコピーしておいた、2003年当時のデータを今回のマスター音源にすることにした。しかし問題はそれだけではなかった。当時のDTMソフトによってレコーディングされたデータのフォーマットが現在多く通用しているものとは違っていて、単に音を聴くためのだけに、コンピュータ関係のサイトをあちこち調べまわらなければならなかった。たった二十年前の20数分の作品を聴くまでに、予想外に長い時間がかかってしまった。
そうして入稿した音源のデータを、レコードと配信、それぞれのマスターにする作業が待っている。今回はフィジカルとデジタルのリリースを同時に行ったのだけど、それぞれのマスタリングに対する考え方は、あえて違ったものにしようと思っていた。
まずレコード。レコードのマスタリングというのはカッティングと同義で、レコードをプレスする元となる「原盤」に文字通り音の溝を切ってゆく工程のこと。2003年のオリジナル7インチは、Exchange という当時のDJ界隈で注目されていた海外のカッティング工場でマスタリングされた。実は僕は最近までそのことを知らなくて、人に教えられて改めて7インチの盤面を見てみると、確かに盤の隅っこに「exchange」という、落書きのような文字が掘られていた(教えてくれた高松のふじたさん、ありがとうございました。僕はなんて無頓着なんだ)。今回どこにカッティング・プレスをお願いするかは、決めていた。mmm とのアルバム CHASING GIANTS を作った際、使用するプリマスタリング音源をどれにするかという段階から相談に乗ってくださったエンジニアさんとぜひ今回も一緒にやりたかったので、川崎の古くからある会社にカッティング・プレスをお願いした。
レコードのカッティングというのは、依頼する度に痛感するけれど、本当に幅広い音が作れるものだ。そして、盤に溝を切るという物理的な作業から生まれる音の変化は、デジタルのように一つのパラメータで一つの音が変わるようなものでなく、一つの要素が音質・音量の全体に常に影響を与えながら曲の印象を形作ってゆく、よりダイナミックで複雑な過程だ。
ここで大事なのがエンジニアさんとのやりとりの仕方だ。ある一点だけを変えてもらおうと思って伝えても、それによって全体が変わるかも知れないということを理解しておかないと、「変えないほうが良かった」ということになりかねない。逆に、変えてほしい点に根拠があるのなら、デジタルのように細かく注文するよりも、ざっくりした表現で伝えた方が、先方により良く意図が伝わるかもしれない。
そして一番大事なのは、カッティングエンジニアさんが作った音を理解し、尊重することだと思う。
海外にカッティングを発注した場合、最初に戻ってくるテストプレスは、こちらの意図と違う部分もあるし部分的に歪んでる場合もあるのだけど、なんだか、エンジニアさんがノリノリでカッティングしてくれたなという雰囲気がその音から伝わってくる時があって面白い。今回は日本語で丁寧にやりとりしたかったから川崎の会社にお願いしたけれど、やりとりの大半は作ってくれた音を変えることではなく、いかに良い部分を残しながら必要な部分だけを変えてもらうかに費やした。例えば A面1曲目の Moonglow は、先方が最初にテストカットしてもらったものを何も変えずに採用している。やはりヴァイナルのカッティングにもセッションのようにテイクがあって、テイク1が一番良いというのはここでも結構言えることなのだ。
こうしてできた盤についてはみなさんのご意見ご感想を、たくさんいただきたいところだ。今のところDJする方々からは、僕が若干不安に思っていた「変えなかったところ」に対して肯定的な感想をいただいている。一方で、聴き比べをした敦賀の方々からは「7インチは現場で楽しみたい時、COVERS 2003 は家で聴きたい時」という感想もいただいた。僕自身はというと、敦賀で聴いた時のレコードプレイヤーはとてもシンプルなものであったにも関わらず、7インチとCOVERS 2003との違いが結構思った通りだったので驚いた。その上で、作品というものを違う環境で聴いた時には必ず新しい発見がある。その「思い通り」と「意外」とのバランスこそが、何度やっても予測のつかない、難しく面白い点なのだ。
デジタルに関してはヴァイナルとは全く違う方向性で、2003 年のマスターの音を、極力忠実にマスター化することを目ざした。2003年というのは、DTMの流れの中では「微妙」な年代だ。カセットが宅録の中心機材だった1980年代や、現在アナログ機以上に使われていない「初期」デジタル機材による1990年代(当時は気づかれなかったが、今思うと音の良い機材がたくさんあった)の録音に比べれば十分現在に近づいているが、現在のようにUSB一本で繋げば思った通りのことができるほどパソコン環境は進んでなくて、「Mac博士くん」がネットに書き込む怪しくて細かい情報を探し回ることが必要だった、そんな時期。
その「微妙」さを伝えるため、きちんとしたマスタリングをしていただくことをあえてせず、ほぼ当時のファイルからのコピーをデジタルのマスターにした(それでも自分なりに、音楽的に必要だと思う調整はした)。それで、サブスクの中で他の楽曲との流れで聴くと若干音量が小さく感じられるかもしれない。「CD時代」のような「音圧競争」が意味をなくした今だからこそできる挑戦かもしれないと思っている。
最近若いミュージシャンの方々から、マスタリングについて尋ねられることがよくある。そもそもレコーディングやミックスと同列でマスタリングという作業をとらえること自体どうかと思うし、ヴァイナル盤の場合はマスタリング(カッティング)とプリマスタリング(デジタル同様、入稿する前の音を調整すること)とは違うというのもあるのだけど、一番思うことは、彼らは「プレビュー」できることが当たり前の環境でずっと音楽をやってきたのだなあということだ。
今ならば録音にしてもミックス・マスタリングにしても、録音した音は演奏した瞬間に、(ほぼ)録音した時のままの音で再生できる。テープレコーダーはそうではなくて、録音された音は録音中に聴いているものとは違うのが当たり前で、それがどんな感じであるか、テープを巻き戻して「再生」ボタンを押すまで分からない。レコードのカッティングも、我々にとっては一度カッティングをしてもらい、テストカット盤をプレイヤーにかけるまでどんな音になっているか分からない。その分からない部分を経験によって予測し、必要な調整をしてくださるのが本来の「エンジニア」さんのエンジニアたる部分だし、我々ミュージシャンの方も、演奏した音と再生される音の差をどう「予測」するか、というか、予測が合っても外れてもそれを作品として伝えてゆく腹の座り方が必要だった。演奏された音と再生される音の差を縮めるためにたくさんの努力が払われ、それが今のレコーディング環境に結実しているのだけど、僕はそもそも、純粋な「演奏したそのままの音」というものがあるのか、あってもそれにどんな価値があるのかよく分からないし、むしろ演奏したままの音と再生される音の「差」の部分から見えてくる、演奏者やエンジニアやレーベルスタッフや音楽ファンの時々の好み・気持ちにこそ音楽の面白さがあると思っている。それがなければモータウンもスタジオ・ワンも存在しなかったはずだから。その差を「予測」しながら、演奏→録音→再生→次の演奏…のサイクルをしりとりのように進めてゆくのが僕の好きな音楽の作り方で、最初から最後まで「自分の思う通り」に進めることが一番という考え方とは違うし、「思い通り」に作ることをサポートしてくれるツールにはあまり興味がないかもしれない。
とにかく、ヴァイナルのマスタリングにおいては、DTMプラグインのように自分が変えたいと思ったポイントだけが変わることはありえなくて、しかもそれは基本的には「再生」してみなければ分からないということは押さえておいていいと思う。物理的に針で盤を刻むという作業から出てくる音は、「レコードの音ってアナログでいい感じですねー」などと言った「アナログ」の印象よりもはるかに幅広く、乱暴で、面白い。僕なりの表現で言わせていただくと、流れる時間の感じがまるで違う。ポータブルなプレイヤー、よく調整されたオーディオ、よく調整されてないオーディオ、クラブの大音響、周りの音に消されそうな少音量、環境によって聴こえる音は違っても、良いマスタリングの施されたレコードは、どんな環境でも音楽の伝わるポイントがなくならない。どんな環境でも同じようなスペックで音が出るストリーミングプラットフォームのためのマスタリングはまたそれとは違っていて、そこにはまた別の挑戦もある。それを良いものにしてゆくのに、演奏の場合にもまして、聴く方々の感想が、しかもそれが思いもよらないものであればあるほど、次の作品に活きてくる。みなさまのご意見・ご感想を、常にお待ちしております。