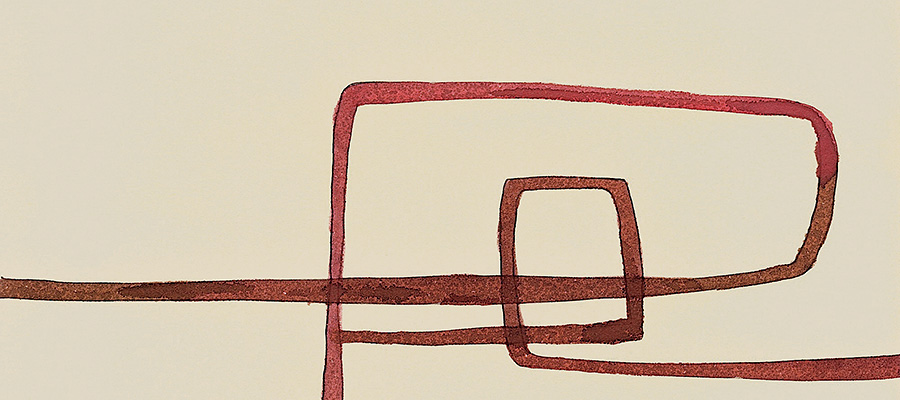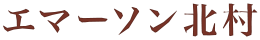1960年代後半、流行した期間はほんの数年だったのに、今もその独特のグルーヴがたくさんの人を引きつける音楽、ロックステディ。その楽曲の中には、同時代の世界中の流行曲をジャマイカの人々の好みに合わせてアレンジした、カヴァーヴァージョンがたくさんありました。アレンジの過程で、その後のレゲエの爆発を用意するシンプルで力強いフレーズがたくさん生まれたのですが、僕がオルガン奏者として尊敬するジャッキー・ミットーは、そのようなフレーズを作ったミュージシャン達の中心人物の一人でした。
僕がエマソロというインスト(インストゥルメンタル。歌のない、器楽演奏の音楽)のソロをやっているのは、基本に彼の影響があります。彼のような音楽をやりたいというところから始まって、彼と彼の仲間が当時の世界の音楽をどう見てどう自分たちのものにしたか、それを今の自分に移してみた時に僕はどんなことができるのか、ということを考えるようになりました。2003年の時点ではだから、カヴァー曲をやることはオリジナル曲と同じくらいの意味を持っていました。オリジナルが中心になった今のエマソロにおいても、そのやり方は同じです。
この音源を再リリースしたのには、2021年のCOVID罹患以降も自分とその近い周りにいろいろあって、なかなか新作音源を発表できない中での苦肉の策という面も、正直ありました。しかし2023年の夏秋いっぱいをかけてリリースの作業をしてみると、単にアーカイブを蔵出しするのとは違った、新作をリリースする時に近い気合いが求められて、やはり、音楽をシーンに「放つ」ということにはそれなりの重さがあるなあ、と改めて思いました。音源(すべてのジャンルの作品もそうでしょう)は、完結した時とリリースされた後とで必ず違う顔を見せるものですが、意思を持って何かを世の中に出すということは、どんなに簡単なものでも、思う以上の作用を自分にも周りにも与えるものですね。それは僕は、大切なことだと思います。
COVERS 2003とオリジナル7インチとの大きな違いのひとつに、アートワークがあります。12インチレコードジャケットの大きさでは7インチのような「ハンコ」を押すことはできないので、ここは最初から異なったものにしようと思い、67531グラフィックスの高宮紀徹さんにデザインをお願いすることにして、さあ打ち合わせをしようという段階になって、自分で撮った写真を使ってもいいかな、と思いました。普段僕は、COVID以降減ったとは言え、街を目的なく歩くのが好きで、その時写真も撮ります。写真を撮る意図はまったくなく、何だか撮っておかなきゃという感じがしたら撮るというだけです。それでも高宮さんの助けを借りて何枚か選んでみて、レコード盤のレーベルにデザインしていただいたら、これが今回自分のやりたかった方向性だったんだと思うことができました。
この写真を撮ったのは大阪で、2022年の秋、ツアーの空き日に一日使って街を歩いた時のものです。本当はとことん徒歩でと思ったんですが昼過ぎから結構本降りの雨になったので、市バスに乗ることにして、バスが橋を渡っている時、窓越しにシャッターを切りました。その橋のたもとはループになっていて、窓から今しがた渡ってきた橋を見上げることができました。バスを降りた後もたくさん歩いたので、傘をさしていたのに足が冷たくなってしまった覚えがあります。
大阪の橋といえば、「大阪の橋ものがたり」という本が大好きで、実際にそれらの橋を知っているわけではないのに、よく読んでいます(東心斎橋のカレー屋さんbuttahのカウンターで見つけて、その後自分で買った)。その中に、昭和初期の本から転載されている「川口端建蔵橋」という橋の写真があって、とても美しいです。雨に濡れた橋上の路面と欄干、向こう岸には工場群があって、橋の上を自転車で渡る人はシルエットになっている。欄干の、何と呼ぶのか、鉄をSの字に曲げた装飾に僕は「弱く」て、2023年に台湾・高雄に行った時に同様の窓枠「鉄窓花」を見て歩いたんですが、(10) に写真を載せた通り、このような装飾とMoonglowのような1930年代の音楽とは何か通じてて、それで好きなのかもしれません。
以上で、COVERS 2003についてのセルフコメントは終わりです。当初リリース前に(1)をアップした時は20年前のことを話そうと思っていたのですが、リリースの後くらいから昔を振り返る気がまったくなくなって(記憶も薄れた)、今の自分が音楽作りについて考えていることがどんどん中心になっていきました。以前は音楽作品に絡めてこういう話をすること自体が好きではなかったのですが、この数年、思っていることを伝えるのに「手段を選ん」でいる場合ではないような気がしてきて、トークイベントをやったりブログを復活させたりしています。同時にこのところは、戦争をやめろ、戦争の準備をやめろ、地震で大変な方々が暮らす土地に原発を作ろうとした人は猛省しろ、といった言葉もずっと自分の中にあります。このレコードを通じて音楽をお伝えすること自体は終わりませんが、作り手の作業としてはひと区切りついたようです。今後はまたライブや、新しい音を作ることでみなさんとお会いできたらと思っています。(2024/01)
エマーソン北村ウエブサイト (column) COVERS 2003 セルフコメント 目次
(1)2003年について
(2)オリジナルリリースについて
(3)再リリースの意味
(4)カヴァーを録音するということ
(5)足鍵盤のオルガンについて
(6)マスタリングについて
(7)カヴァー曲紹介 B1 You’ll Never Find
(8)カヴァー曲紹介 B2 Polka Dots and Moonbeams
(9)カヴァー曲紹介 B3 Who Done It
(10)カヴァー曲紹介 A1 Moonglow
(11)カヴァー曲紹介 A2 Green Dolphin Street
(12)カヴァー曲紹介 A3 Ram Jam
(13)もくじと、アートワークについて(このページ)