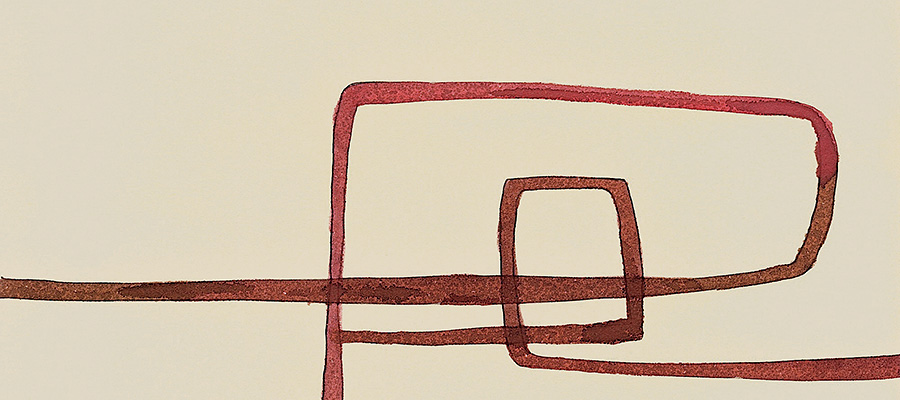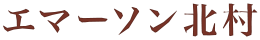COVERS 2003 B3 (デジタルでは6曲目) Who Done It (Jackie Mittoo, C. S. Dodd)
この曲は2003年に7インチでリリースされた時にはMidnight Confessionというタイトルがついていた。今回それを修正して、Who Done Itとした。そのいきさつはこんなことだ。
Midnight ConfessionはU Brownが歌ったダンスホールチューンで、Trojan Dancehall Box SetというコンピレーションCDに入っていた。そのリズムトラックは実はジャッキー・ミットーのWho Done Itというインスト曲で、彼のファーストアルバムIn Londonにも入っているから聴いたことはあったのだけど、トラックの常としてテンポもサウンドも違うものになっていたのでつい気がつかず、歌(というかDJ=トースティング)のタイトルであるMidnight Confessionをそのまま僕のヴァージョンにも使った。後からあれはミットーのインスト曲だったと気づいて、機会があったら直さなければとずっと思っていた。誰がどのリディム(リズムトラック)を使ってそのオリジナルは何か、詳しい方がたくさんいるのだけど、僕はどうもこの問題になると何だか認識の裂け目にはまったようになって頭がぼんやりしてしまう。申し訳ないです……
ところでミットーのWho Done Itにもオリジナルというか「リユース元」があって、それはUSのサックス奏者でプロデューサーのMonk Higginsが作ったWho-Dun-It?というインスト曲だ。元曲が1966年にリリースされ、ミットーとスタジオワンのミュージシャンが自分たちのヴァージョンを発表するのが67年。当然ながらネットもなく輸入レコードだけが唯一のアメリカ音楽の情報源だった時代に、このリアクションの速さと的確さは何だろう。元曲もソウルジャズというかブルージーで踊れるいい曲なのだけど、ミットー達のヴァージョンは、余分な音のなさ、各パート間のタイミングの妙、そしてサックスを置き換えたオルガンのカッコよさにおいて、作曲者の名義を主張できるだけのオリジナリティを持っている。ひとことで言うとミットー達は、ループを演奏することの意識において、当時のUSのミュージシャンよりもはるかに現代に近いところにいると思う。
曲名問題を調べているうち、ジャッキー・ミットーについての論文があることをネットで見つけた。カレン・サイラスという方がカナダ・トロントのヨーク大学で書いたものとのこと
Jackie Mittoo At Home and Abroad: The Cultural and Musical Negotiations of a Jamaican Canadian
https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/30656
僕の英語力はゆ〜っくり辞書を引きながら読めば大体の文意が想像できる程度なので、よっぽど時間がなければ読めないだろうと思っていたところ、2021年の夏にCOVIDになってしばらく寝こむ日々が続いたので、その機会に全部ではないけれど読んでみた。音楽論の前提となるミットーのバイオグラフィーがまず面白くて、今まで知らないことがたくさんあって、昨年今年のトークでは随分使わせてもらった。
この論文では、外からの文化が元の文化と出会う時、お互いに変化を与え・与えられながら担い手にとって自分達のものとなってゆく過程を丁寧に分析していて、楽曲の「リユース」についても、その過程で用いられる文化の担い手側の「戦略」のひとつとして論じられている。Who-Dun-It?→Who Done Itはその具体例として取り上げられていた。ミットー自身の生まれ育ちとその時代のジャマイカ(後には移住したカナダ・トロント)の社会や文化がどんな風に関わって彼の音楽となり、それがまた音楽シーンに影響を与えてゆくことになったか、バイオグラフィー上のエピソードの面白さとともに、いろんなことに考えをめぐらすことのできる論文だった。
僕のヴァージョン独自のアレンジであるドラムボックスのフレーズについて、どうしてこうしたかったんだったっけとデータを探していたら、ニューヨークのハウス・アーティストであるMasters at Workのサンプリングなどを試しているのを見つけた。僕にとってはニューヨリカン・ソウルとしての方がなじみのある人たち。その頃僕は結構いろいろなものをサンプリングしていて、後にいうトラックメーキングの練習などをしていたようだが、今日、デモを発見するまですっかり忘れていた。ある時これは自分には無理だと気がついて、その後はドラムボックスの音だけで演奏する安心感の方に進んだのだけど、二十年前の僕は、今よりまっしぐらに「クラブミュージック」寄りだったのだなあ。その後の僕の進み方、どうなんだろ。


Who Done Itも入っているミットーのコンピレーション、Tribute To Jackie Mittooの裏表紙。いいですね。