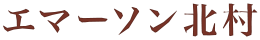こちら、solo/label 覧の記事をご覧ください。
https://www.emersonkitamura.com/solo/?p=848
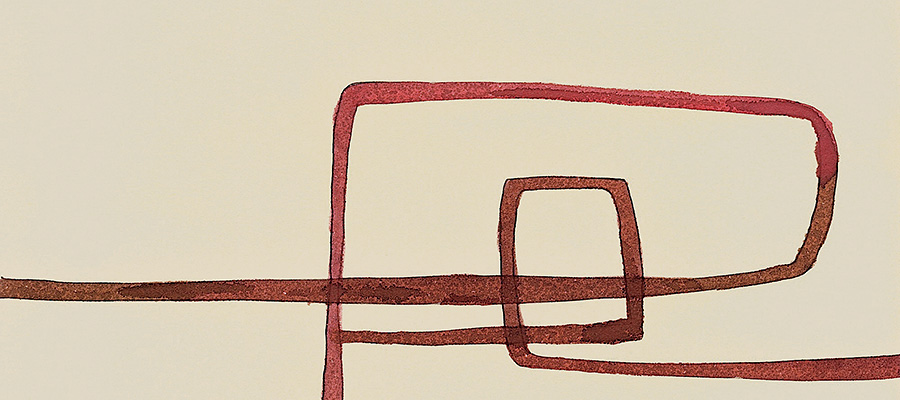
Emerson Kitamura
Column
2024.02.07 Wed
マニュエル・ビアンヴニュの新アルバムをカセットとCDでリリースします。
2024.01.11 Thu
COVERS 2003(13)目次と、アートワークについて
1960年代後半、流行した期間はほんの数年だったのに、今もその独特のグルーヴがたくさんの人を引きつける音楽、ロックステディ。その楽曲の中には、同時代の世界中の流行曲をジャマイカの人々の好みに合わせてアレンジした、カヴァーヴァージョンがたくさんありました。アレンジの過程で、その後のレゲエの爆発を用意するシンプルで力強いフレーズがたくさん生まれたのですが、僕がオルガン奏者として尊敬するジャッキー・ミットーは、そのようなフレーズを作ったミュージシャン達の中心人物の一人でした。
僕がエマソロというインスト(インストゥルメンタル。歌のない、器楽演奏の音楽)のソロをやっているのは、基本に彼の影響があります。彼のような音楽をやりたいというところから始まって、彼と彼の仲間が当時の世界の音楽をどう見てどう自分たちのものにしたか、それを今の自分に移してみた時に僕はどんなことができるのか、ということを考えるようになりました。2003年の時点ではだから、カヴァー曲をやることはオリジナル曲と同じくらいの意味を持っていました。オリジナルが中心になった今のエマソロにおいても、そのやり方は同じです。
この音源を再リリースしたのには、2021年のCOVID罹患以降も自分とその近い周りにいろいろあって、なかなか新作音源を発表できない中での苦肉の策という面も、正直ありました。しかし2023年の夏秋いっぱいをかけてリリースの作業をしてみると、単にアーカイブを蔵出しするのとは違った、新作をリリースする時に近い気合いが求められて、やはり、音楽をシーンに「放つ」ということにはそれなりの重さがあるなあ、と改めて思いました。音源(すべてのジャンルの作品もそうでしょう)は、完結した時とリリースされた後とで必ず違う顔を見せるものですが、意思を持って何かを世の中に出すということは、どんなに簡単なものでも、思う以上の作用を自分にも周りにも与えるものですね。それは僕は、大切なことだと思います。
COVERS 2003とオリジナル7インチとの大きな違いのひとつに、アートワークがあります。12インチレコードジャケットの大きさでは7インチのような「ハンコ」を押すことはできないので、ここは最初から異なったものにしようと思い、67531グラフィックスの高宮紀徹さんにデザインをお願いすることにして、さあ打ち合わせをしようという段階になって、自分で撮った写真を使ってもいいかな、と思いました。普段僕は、COVID以降減ったとは言え、街を目的なく歩くのが好きで、その時写真も撮ります。写真を撮る意図はまったくなく、何だか撮っておかなきゃという感じがしたら撮るというだけです。それでも高宮さんの助けを借りて何枚か選んでみて、レコード盤のレーベルにデザインしていただいたら、これが今回自分のやりたかった方向性だったんだと思うことができました。
この写真を撮ったのは大阪で、2022年の秋、ツアーの空き日に一日使って街を歩いた時のものです。本当はとことん徒歩でと思ったんですが昼過ぎから結構本降りの雨になったので、市バスに乗ることにして、バスが橋を渡っている時、窓越しにシャッターを切りました。その橋のたもとはループになっていて、窓から今しがた渡ってきた橋を見上げることができました。バスを降りた後もたくさん歩いたので、傘をさしていたのに足が冷たくなってしまった覚えがあります。
大阪の橋といえば、「大阪の橋ものがたり」という本が大好きで、実際にそれらの橋を知っているわけではないのに、よく読んでいます(東心斎橋のカレー屋さんbuttahのカウンターで見つけて、その後自分で買った)。その中に、昭和初期の本から転載されている「川口端建蔵橋」という橋の写真があって、とても美しいです。雨に濡れた橋上の路面と欄干、向こう岸には工場群があって、橋の上を自転車で渡る人はシルエットになっている。欄干の、何と呼ぶのか、鉄をSの字に曲げた装飾に僕は「弱く」て、2023年に台湾・高雄に行った時に同様の窓枠「鉄窓花」を見て歩いたんですが、(10) に写真を載せた通り、このような装飾とMoonglowのような1930年代の音楽とは何か通じてて、それで好きなのかもしれません。
以上で、COVERS 2003についてのセルフコメントは終わりです。当初リリース前に(1)をアップした時は20年前のことを話そうと思っていたのですが、リリースの後くらいから昔を振り返る気がまったくなくなって(記憶も薄れた)、今の自分が音楽作りについて考えていることがどんどん中心になっていきました。以前は音楽作品に絡めてこういう話をすること自体が好きではなかったのですが、この数年、思っていることを伝えるのに「手段を選ん」でいる場合ではないような気がしてきて、トークイベントをやったりブログを復活させたりしています。同時にこのところは、戦争をやめろ、戦争の準備をやめろ、地震で大変な方々が暮らす土地に原発を作ろうとした人は猛省しろ、といった言葉もずっと自分の中にあります。このレコードを通じて音楽をお伝えすること自体は終わりませんが、作り手の作業としてはひと区切りついたようです。今後はまたライブや、新しい音を作ることでみなさんとお会いできたらと思っています。(2024/01)
エマーソン北村ウエブサイト (column) COVERS 2003 セルフコメント 目次
(1)2003年について
(2)オリジナルリリースについて
(3)再リリースの意味
(4)カヴァーを録音するということ
(5)足鍵盤のオルガンについて
(6)マスタリングについて
(7)カヴァー曲紹介 B1 You’ll Never Find
(8)カヴァー曲紹介 B2 Polka Dots and Moonbeams
(9)カヴァー曲紹介 B3 Who Done It
(10)カヴァー曲紹介 A1 Moonglow
(11)カヴァー曲紹介 A2 Green Dolphin Street
(12)カヴァー曲紹介 A3 Ram Jam
(13)もくじと、アートワークについて(このページ)

2024.01.05 Fri
COVERS 2003(12)カヴァー曲紹介 A3 Ram Jam
COVERS 2003 A3 Ram Jam (Jackie Mittoo, C. S. Dodd)
カヴァー曲紹介も最後になり、ついにRam Jamを取り上げる時が来た。いうまでもなくジャッキー・ミットーの最も有名で、いちばんシンプルだけど一番さまざまな気分が盛り込まれている曲。MUTE BEATでの僕の先任のキーボーディスト、朝本浩文さんのユニット名にもありました。
シンプルという印象に反して、やってみると意外に難しい曲。いや、単にやるだけならシンプルなのだけど、曲を自分のものにしようとするとたくさん「?」な点が出てきて、大事なところはその間からすり抜けてしまう。例えばコード。主メロである和音と、伴奏を構成するコード進行の和音とが一致しない。不協和音ではないけれど、主メロとコード進行との費やす時間がずれていて、バンドでなら気にならないのだけど一人だと意外に悩んでしまう。COVERS 2003の僕の演奏はそこがオリジナルと違うのだけど、気がつくだろうか?ロックステディを代表すると思われているベースラインにしても、かつて一度、リロイ・シブルス(ヘプトーンズのヴォーカリストだがスタジオ・ワンのベーシストでもあり、多数の有名トラックのベースを担当してきた)がこの曲のベースラインを説明する、という夢のようなシーンに出くわしたことがあるのだが、思っていたのとは違うなんだかふんわりした話で終わって、拍子抜けしたことがある。僕はUSで活動してきたミュージシャンがするような「俺の作ったこのフレーズはこう弾くのが肝心で……」のような説明を期待していたのだと思うけど、きっと彼のミュージシャンシップはそういう部分にはないのだろう。
だからといって、レゲエが不明確なところの多い、いい加減な音楽だとは思わない。いや、不明確なところは多いのだけど、それを僕ら(元からその音楽を担っているわけではない)演奏者の都合で「ここはいい加減に」と済ませてしまっては、肝心のフレーズの「強度」はいつまでたっても生まれないのではないかな。多少面倒に思われようとも「ここのコードは何なんすかー、このリズムはどうなってるんですか?」とあくまで音楽的に自分のものにしようとすることでしか、人に伝わるものを作れるようにならないのではと思っている。それが結果的にレゲエにジャンル分けされようがされまいが。
何度かトークイベントでも話して、このセルフコメントでも(9)に登場しているJackie Mittoo at Home and Abroadという論文では、Ram Jamが1950~60年代に流行したキューバ音楽をモチーフにしたポップス曲、Poincianaをリユースしていると述べられているのだけど、PoincianaのどこがRam Jamにリユースされているのか、僕はいまだに分かっていない。多分、USのピアニストであるアーマッド・ジャマル(2023年に亡くなりました)がライヴ盤に残している演奏の冒頭部分のことではないかと思うのだけど、ただはっきりと分からなくても、Poincianaの、そして多分アーマッド・ジャマルの、柔らかいがはっきりしたグルーヴの中からさまざまな色彩が浮かんでくるような「雰囲気」は確かにミットーに受け継がれていて、そこにロックな世代の気分とシンプルさが付け加えられてRam Jamとして形をなした、と想像することもできるだろう。音楽と音楽のつながりにおいてこういう「雰囲気」は決して(コードのように)不明確なものではなくて、ちゃんと、ミュージシャンがイメージして形にできるはずのものだ……余分なことに気をとられなければ。
想像ついでに。上記の論文で僕が初めて知ったことの一つに、ジャッキー・ミットーが子供のころ学校の催しでピアノを弾いたことがあり、その時の曲は当時の映画音楽Theme From A Summer Placeだったという話がある。この曲は後にTan Tan (EddieThornton)やMUTE BEATもレパートリーにしたレゲエで最も多くカヴァーされる曲のひとつだけど、そのはるか以前にミットーが弾いていたというエピソードは、なぜか僕に強いイメージを与える。この曲やPoincianaにはなにか、目に見えるものからほんの少し先が透けているような、ちょっとだけ非現実的な感じがある。それを弾いていたミットーがミュージシャンになって生み出したのは、外でもない現実を生きる人のための音楽であるスカやロックステディ、そしてレゲエだった。だけど自分が作曲する時には、どこかで常に、昔自分が弾いたイージーリスニングのような、ちょっと非現実感な何かもいっしょに抱いていたのではないかな。ミットーの演奏を聴くと僕はいつもそんな感じがする。

2024.01.05 Fri
COVERS 2003(11)カヴァー曲紹介 A2 Green Dolphin Street
COVERS 2003 A2 Green Dolphin Street (Bronislaw Kaper-Ned Washington)
たぶん収録曲の中で一番有名な曲だと思うが、僕にとっては一番なじみのない曲だった……僕はメインストリームのジャズを実践する場にいたことがまったくなくて、このような曲を人から教えてもらうといった、普通のミュージシャンなら若いうちに経験するはずのことが、すっぽり抜けていたりする。音源を聴いても、慣れないジャズ的な表現に苦しんでいるのか、たどたどしいところがたくさんある。ただ、有名曲という認識がなかっただけでこの曲をやりたくなかったわけではなく、むしろ「良いマテリアルを見つけたぜ!」と一人で喜んでいた。そんな経緯やドラムのフレーズ(まただ)などからして多分、COVERS 2003の全体を通して最も1990年代感をかもし出しているトラックなのではないかと思う。でもライブでは喜んでくれる方が多い。自分が気になるポイントというのはいつも、単に自意識のなせるものだからなあ……
とにかく、どうやってGreen Dolphin Streetを見つけたかというと、Lou Bennettというオルガンプレイヤーのアルバムでだった。USで活動した後フランスに渡り、そのままずっとヨーロッパで演奏し続けた人だそうだ。改めて彼のレコードを聴いてみると、僕がやっていることはグルーヴが違っているだけで、かなり「そのまま」だ。彼の演奏は音色がいいです。機材的な話で恐縮だが、オルガンといえば回転スピーカ(レズリースピーカという)を使って熱くステレオワイドに拡がる音、というのが最も「らしい」演奏とされているけど、僕にはあまり興味がない。この演奏のようにほとんどスピーカを「回さない」素のような音にむしろグルーヴが感じられて、とても好みだ。1990年代の日本で1960年代のオルガンジャズを再評価する動きがあり、僕も一時期だけ結構マニアックにレコードを買った。そのマニア心が行き着いて取り上げた一曲、と思っていただけたらありがたいです。



Lou Bennett – AMEN (1960)
2024.01.05 Fri
COVERS 2003(10)カヴァー曲紹介 A1 Moonglow
COVERS 2003 A1 Moonglow (Will Hudson-Eddie DeLange-Irving Mills)
オリジナルの7インチでもCOVERS 2003でも冒頭のトラックとなったこの曲が、一番、カヴァー元と自分のヴァージョンの距離があるかもしれない。僕がこの曲を始めて聴いたのは1970年代にいたるところに存在した「魅惑のスクリーンミュージック」的なLPの一枚で、「ピクニック」という映画のサウンドトラックとしてだった(映画は観たことがない)。熱を出して学校を休んだ昼などによく聴いていたのだけど、ゴージャスな(と当時は思った)映画音楽が並ぶ中でこの曲になると急に音にスキマができて、そのツーンとした雰囲気が好きだった。後になって、この曲は映画よりさらに以前、スイングジャズの時代に作られたということを知った。
この曲をスタンダードにしたのは何といってもベニー・グッドマンの演奏によるだろう。僕は特に、彼がテディ・ウィルソンとジーン・クルーパのトリオにライオネル・ハンプトンを加えて録音したスモール・グループの音源が好きだ。このグループはメインであるビッグバンドの幕間用編成にもかかわらず「進んだ」バンドであった、というのがジャズ界での評価らしい。僕の感覚で聴くと、このバンドの人間関係はすごく今のロックバンドに近かったのではないかと想像してしまう。パッと聴きは調和していて優美なのに、いつもどこか緊張をはらんでいる。四人という数も絶妙。そして僕がとにかく好きなライオネル・ハンプトンのヴィブラフォンが素晴らしい。
ベニー・グッドマンのヴァージョンと僕のヴァージョンの間には、それらとは全然似ていない、でもこれも素晴らしいヴァージョンが挟まっている。1960年代に盛り上がったグルーヴィなオルガンジャズのプレイヤー、ジミー・マグリフの演奏だ。踊るための音楽で、ジュークボックスでかけられることを前提としたレコードを数多く作ったGroove Merchantというレーベルのアーティストの中でも、オルガンという楽器を一番上手に活かした人。もちろんリズムはファンクなのだけど、コード進行のアレンジが他にはない四度シャープから半音ずつ降りてゆく(階名で読むとファ#→ファ→ミ→レ……)、それだけを取り出すと静謐とも言える進行で、これと強いグルーヴを組み合わせるというアイデアは、僕もしっかり影響を受けている。数ある音楽スタイルの中で「何を」やるかということは僕にとってはあまり大事でなくて、スタイルを構成する音楽要素にまでさかのぼった時にそれを「どう」表すか、にアレンジの面白さはあると思っている。大抵こんがらがってしまうけど。
ドラムボックスのフレーズは込み入ったオルガンのアレンジとは逆に、はっきりとRhythm & Sound的なダブ・テクノの影響が分かる。やっぱり時代感がここに現れている。冒頭からずっと聴こえる低い音は、ローランドのSystem 100というシンセ。もう40数年使っている。


2023.12.31 Sun
COVERS 2003(9)カヴァー曲紹介 B3 Who Done It
COVERS 2003 B3 (デジタルでは6曲目) Who Done It (Jackie Mittoo, C. S. Dodd)
この曲は2003年に7インチでリリースされた時にはMidnight Confessionというタイトルがついていた。今回それを修正して、Who Done Itとした。そのいきさつはこんなことだ。
Midnight ConfessionはU Brownが歌ったダンスホールチューンで、Trojan Dancehall Box SetというコンピレーションCDに入っていた。そのリズムトラックは実はジャッキー・ミットーのWho Done Itというインスト曲で、彼のファーストアルバムIn Londonにも入っているから聴いたことはあったのだけど、トラックの常としてテンポもサウンドも違うものになっていたのでつい気がつかず、歌(というかDJ=トースティング)のタイトルであるMidnight Confessionをそのまま僕のヴァージョンにも使った。後からあれはミットーのインスト曲だったと気づいて、機会があったら直さなければとずっと思っていた。誰がどのリディム(リズムトラック)を使ってそのオリジナルは何か、詳しい方がたくさんいるのだけど、僕はどうもこの問題になると何だか認識の裂け目にはまったようになって頭がぼんやりしてしまう。申し訳ないです……
ところでミットーのWho Done Itにもオリジナルというか「リユース元」があって、それはUSのサックス奏者でプロデューサーのMonk Higginsが作ったWho-Dun-It?というインスト曲だ。元曲が1966年にリリースされ、ミットーとスタジオワンのミュージシャンが自分たちのヴァージョンを発表するのが67年。当然ながらネットもなく輸入レコードだけが唯一のアメリカ音楽の情報源だった時代に、このリアクションの速さと的確さは何だろう。元曲もソウルジャズというかブルージーで踊れるいい曲なのだけど、ミットー達のヴァージョンは、余分な音のなさ、各パート間のタイミングの妙、そしてサックスを置き換えたオルガンのカッコよさにおいて、作曲者の名義を主張できるだけのオリジナリティを持っている。ひとことで言うとミットー達は、ループを演奏することの意識において、当時のUSのミュージシャンよりもはるかに現代に近いところにいると思う。
曲名問題を調べているうち、ジャッキー・ミットーについての論文があることをネットで見つけた。カレン・サイラスという方がカナダ・トロントのヨーク大学で書いたものとのこと
Jackie Mittoo At Home and Abroad: The Cultural and Musical Negotiations of a Jamaican Canadian
https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/30656
僕の英語力はゆ〜っくり辞書を引きながら読めば大体の文意が想像できる程度なので、よっぽど時間がなければ読めないだろうと思っていたところ、2021年の夏にCOVIDになってしばらく寝こむ日々が続いたので、その機会に全部ではないけれど読んでみた。音楽論の前提となるミットーのバイオグラフィーがまず面白くて、今まで知らないことがたくさんあって、昨年今年のトークでは随分使わせてもらった。
この論文では、外からの文化が元の文化と出会う時、お互いに変化を与え・与えられながら担い手にとって自分達のものとなってゆく過程を丁寧に分析していて、楽曲の「リユース」についても、その過程で用いられる文化の担い手側の「戦略」のひとつとして論じられている。Who-Dun-It?→Who Done Itはその具体例として取り上げられていた。ミットー自身の生まれ育ちとその時代のジャマイカ(後には移住したカナダ・トロント)の社会や文化がどんな風に関わって彼の音楽となり、それがまた音楽シーンに影響を与えてゆくことになったか、バイオグラフィー上のエピソードの面白さとともに、いろんなことに考えをめぐらすことのできる論文だった。
僕のヴァージョン独自のアレンジであるドラムボックスのフレーズについて、どうしてこうしたかったんだったっけとデータを探していたら、ニューヨークのハウス・アーティストであるMasters at Workのサンプリングなどを試しているのを見つけた。僕にとってはニューヨリカン・ソウルとしての方がなじみのある人たち。その頃僕は結構いろいろなものをサンプリングしていて、後にいうトラックメーキングの練習などをしていたようだが、今日、デモを発見するまですっかり忘れていた。ある時これは自分には無理だと気がついて、その後はドラムボックスの音だけで演奏する安心感の方に進んだのだけど、二十年前の僕は、今よりまっしぐらに「クラブミュージック」寄りだったのだなあ。その後の僕の進み方、どうなんだろ。


Who Done Itも入っているミットーのコンピレーション、Tribute To Jackie Mittooの裏表紙。いいですね。
2023.12.28 Thu
COVERS 2003(8)カヴァー曲紹介 B2 Polka Dots and Moonbeams
B2 (デジタルでは5曲目) Polka Dots and Moonbeams (Jimmy Van Heusen-Johnny Burke)
1920~40年代のジャズが好きになったきっかけは、何だったかな。パンクの時代にロックンロールのはじまりを探すみたいな話題があって、ルイ・ジョーダンらのジャンプジャズや映画「ストーミー・ウェザー」のニコラス・ブラザーズのダンスがプリミティブを求める気分にぴったりだった時もあったけど、さらに思い出すと子供の頃にTVか何かで「グレン・ミラー物語」をそれと知らず観ていた気もするし、それを言うなら3才にも満たない頃に観ていた「トムとジェリー」は今思うと’40年代ビッグバンドのアレンジにあふれていて、そんな子供にしてもスピード感のあるリズムとちょっと怖い時もある和音が強く印象に残ったし、実際後から調べたら劇中でトムが”Is You Is or Is You Ain’t My Baby”(ルイ・ジョーダン。ただし演奏は別)を歌うシーンもあったり、とにかく意外とマニアックにならずに、モダンジャズ以前のジャズに触れる機会はその年代の子供にはあったのだ。
COVERS 2003の頃は僕のそんな好みがさらに拡がって、ジャンプジャズなどからさらに、室内楽的なビッグバンドへと興味が向いていた時期だった。そして見つけたのがクロード・ソーンヒル楽団で、ヴォーカルグループをフィーチャーした”There’s A Small Hotel”も好きだったけど、イントロから和声のアレンジがすごかったのでこれをオルガン一台でできないかと思い、Polka Dots and Moonbeamsをカヴァーすることにした。
和声に加えてやりたかったこととして、リズムはとてもオーソドックスな、電子オルガンのリズムボックスに入っているようなリズムを使った。今もエマソロで多用するこのようなドラムボックスのリズムの妙な「安心感」って、何なんだろう。もはや自分に近すぎでその意味を思い出すことすらできない。ただしこの曲だけで使っている要素もあって、シンセで作ってTR-808に加えているリズムの音で目指したかった雰囲気は、ずばり、YMOの「シムーン」だ。ある年代の人には近すぎて意識できないのだけど、やはりエマソロにはYMOの影響があるのだと思う。
自分のオルガンではすっかり音数が減ってしょぼくなってしまったイントロを始めとする原曲のアレンジは、当時同バンドのアレンジャーをしていたギル・エヴァンスによるもの。後にマイルス・デイヴィスとのコラボレーションで有名になるあの人だ。最近きっかけがあってまた彼のアルバム「The Individualism of …」を聴いているのだけど、和声とリズムの両面においてとことん「にじみ」を追求したんだなあとつくづく思う。彼の表現方法は譜面を書くことだからアドリブ中心のジャズにおいてはパフォーマーとは違った立場で受け取られることもあるようだけど、単音の楽器で即興的にメロディを作るということとは違った「瞬間」の表わし方がジャズ(やそれ以外の音楽)にはあるのだということを、彼の音楽から気づくことができると思う。
今年行ったCOVERS 2003発売にまつわるエマソロライヴでは、気に入ってくださる方の多い曲でもあった。


“Polka Dots and Moonbeams”が入っているアルバムではないのだけど、アートワークが良かったので。
2023.12.28 Thu
COVERS 2003(7)カヴァー曲紹介 B1 You’ll Never Find
B1 (デジタルでは4曲目) You’ll Never Find (Kenneth Gamble, Leon A. Huff)
JAGATARAのベーシストで尊敬する友達でもあったNABEちゃんが「俺はねえ、初めて買ったLPは必ずB面からかけるんだよ〜」と言っていたのにならって、ヴァイナルをまとめる作業はいつもB面から始めることにしている。なのでカヴァーの元曲を紹介するのもこのトラックから。
COVERS 2003には、ジャッキー・ミットーのような演奏をストレートにやりたいと思って選んだ曲と、表面上はレゲエでなくても姿勢は彼らのやり方にのっとってやろうとした曲との2タイプが、ちょうど半分ずつ収録されている。この曲はあきらかに前者で、ジャッキー・ミットーのアルバムThe Keyboard Kingで僕がはじめて聴いたこの曲のアレンジをお手本にしている。
ミットーのトラックそのものがカヴァーで、オリジナルはギャンブル・ハフのソングライティングチームが作曲してルー・ロウルズが歌ったソウル・チューン、1976年のYou’ll Never Find Another Love like Mineだ。ミットーのヴァージョンは、レゲエシンガーのJohn Holtによるカヴァーのためにバニー・リーのプロダクションで彼達が演奏した音源から、レゲエではしごく普通のことだけど、リズムトラックだけを再使用して自分のオルガンを重ねている(ヴォーカルもダブ要素として登場している)。つまり僕のトラックは、USで制作されたソウル→のレゲエシンガーのカヴァー→のオルガンヴァージョン→をカヴァーした、四代目?のヴァージョンとなる。
この曲をとりあげようと思った理由は、その「レゲエらしくないのにレゲエ以外の何物でもない」グルーヴだ。スライ・ダンバーのシンコペーションばかりのドラムフレーズと、ロビー・シェイクスピアの、コードのメジャー7th音(コードのルートからドレミファソラシと数えたときのシ)から始まるベースラインという、普通なら避けるべきことだらけの演奏なのに、全体としては見事に成り立っている不思議なリズムアレンジ。しかもそのリズム・コード共にモヤがかかったような雰囲気から生まれるグルーヴは強くしなやかで、原曲のフィリー・ソウルよりもバネがある。ジャッキー・ミットーのオルガンも、それだけを取り出して聴けばまったくイージーリスニングというか、この時代によくあるポップスのオルガン演奏なのに、リズム隊と一緒になるとたちまちグルーヴを発揮する。このオルガンと他のオルガンの違いは何なのか、2000年代ならば「音色」と答える人もあっただろうが僕はそう思わない。伸ばす音と短く切る音の配置とタイミング、そして原曲の歌のようなそうでないような微妙なメロディ、つまりはジャッキー・ミットー自身の「音符」そのものが、ドラムアンドベースと一緒になった時に他にはないグルーヴを生み出しているのだ。おそらく全員が同時代のUSのソウルやファンクの演奏をタイムラグなしで身につけているはず。そこから出てくるファンクのエッセンスが、ワンドロップなどひとつもないのにレゲエでしかないグルーヴを感じさせるということが、ヒップホップも4つ打ちもなかった時代の十六分音符の演奏の凄みと幅広さを表わしている。
この雰囲気を何とか自分のものにしたい、という極めてストレートな気持ちで取り組んだのだけど、やり方がストレートすぎて、足鍵盤とメロディの音域が重なっても気にしてなかったり、普通ならもっと分かりやすくすべき工夫をまったくしなかったので、聴こえてくる演奏はまったくストレートではなくなってしまった。リズムマシンTR-808のフレーズだけは少し整理しているのだけど、その方向性には僕の1980年代ニューウエーブから1990年代にかけての感覚がうかがわれる。この傾向はCOVERS 2003の全体にあって、収録曲のアレンジから「時代感」を感じるとしたらまず打ち込みドラムのパターン(だけ)ではないかと思う。ドラムのフレーズというものはそういう風に手がかりとされがちなので、ちょっと可哀想だ。それなら、大好きなピューンというシンドラも入れておけばよかった。
ヴァイナルのマスタリングでは、とにかくキックに注目して全体の感じを決めていった。強く、しかし、ローエンドが出すぎて重くならないように。重さは足鍵盤に担当させて、バネを持って音楽を進めてくれるように。イントロの二発のキックとシンバルだけで(TR-808ではこういうイントロが作れる)、続くB面のすべての音をうまく導いてくれるようにと願って作った。

Jackie Mittoo The Keyboard King
https://www.discogs.com/release/2388181-Jackie-Mitto-The-Keyboard-King
2023.11.09 Thu
COVERS 2003(6)マスタリングについて
先日、敦賀でのエマソロイベントで、COVERS 2003 の発売以来、最もハラハラする瞬間があった。
地元のDJチームの方が、二十年前から持っていたオリジナルの7インチと購入されたばかりの COVERS 2003 とを二台のターンテーブルに乗せて、その音質を聴き比べるという場面に出くわしたのだ。まさにこんな機会もあろうかと、この夏はカッティングエンジニアさんと何度もやりとりしてきたのだ、とひそかに思いながら、一方で、再発の方が音が悪かったらどうしようと不安でもあった。結果は、思ったとおりでもあり、意外でもあり……でもマスタリングされた作品の音というのはそれで良くて、むしろ「思った通り」だけではつまらないと考えている。そのことはこの欄の最後に書きたい。とにかく yoiyoi クルーの皆様、ありがとうございました!
COVERS 2003 のマスタリングを行うにあたって、最近ではすっかりやらなくなった作業から始めることになった。マスターテープを探すことだ。ハードディスクではなく物理的に家の中でものを探すという行動自体が久しぶりだった。そして、当時の DAT テープを発見した(写真)。見たことのない人も多いと思う。カセットテープの7割くらいの大きさで、テープだけどデジタルデータを記録している。
しかし結局、このテープを今回の元音源とすることはできなかった。家にもカッティングをお願いした工場にも、DAT を安全に再生できるプレイヤーがなかったのだ。再生できないというよりも、テープが機械の内部で絡まって切れてしまうような危険性を考えると、テープをかけること自体が一種の賭けになってしまうからだ。結局、このテープをハードディスクにコピーしておいた、2003年当時のデータを今回のマスター音源にすることにした。しかし問題はそれだけではなかった。当時のDTMソフトによってレコーディングされたデータのフォーマットが現在多く通用しているものとは違っていて、単に音を聴くためのだけに、コンピュータ関係のサイトをあちこち調べまわらなければならなかった。たった二十年前の20数分の作品を聴くまでに、予想外に長い時間がかかってしまった。
そうして入稿した音源のデータを、レコードと配信、それぞれのマスターにする作業が待っている。今回はフィジカルとデジタルのリリースを同時に行ったのだけど、それぞれのマスタリングに対する考え方は、あえて違ったものにしようと思っていた。
まずレコード。レコードのマスタリングというのはカッティングと同義で、レコードをプレスする元となる「原盤」に文字通り音の溝を切ってゆく工程のこと。2003年のオリジナル7インチは、Exchange という当時のDJ界隈で注目されていた海外のカッティング工場でマスタリングされた。実は僕は最近までそのことを知らなくて、人に教えられて改めて7インチの盤面を見てみると、確かに盤の隅っこに「exchange」という、落書きのような文字が掘られていた(教えてくれた高松のふじたさん、ありがとうございました。僕はなんて無頓着なんだ)。今回どこにカッティング・プレスをお願いするかは、決めていた。mmm とのアルバム CHASING GIANTS を作った際、使用するプリマスタリング音源をどれにするかという段階から相談に乗ってくださったエンジニアさんとぜひ今回も一緒にやりたかったので、川崎の古くからある会社にカッティング・プレスをお願いした。
レコードのカッティングというのは、依頼する度に痛感するけれど、本当に幅広い音が作れるものだ。そして、盤に溝を切るという物理的な作業から生まれる音の変化は、デジタルのように一つのパラメータで一つの音が変わるようなものでなく、一つの要素が音質・音量の全体に常に影響を与えながら曲の印象を形作ってゆく、よりダイナミックで複雑な過程だ。
ここで大事なのがエンジニアさんとのやりとりの仕方だ。ある一点だけを変えてもらおうと思って伝えても、それによって全体が変わるかも知れないということを理解しておかないと、「変えないほうが良かった」ということになりかねない。逆に、変えてほしい点に根拠があるのなら、デジタルのように細かく注文するよりも、ざっくりした表現で伝えた方が、先方により良く意図が伝わるかもしれない。
そして一番大事なのは、カッティングエンジニアさんが作った音を理解し、尊重することだと思う。
海外にカッティングを発注した場合、最初に戻ってくるテストプレスは、こちらの意図と違う部分もあるし部分的に歪んでる場合もあるのだけど、なんだか、エンジニアさんがノリノリでカッティングしてくれたなという雰囲気がその音から伝わってくる時があって面白い。今回は日本語で丁寧にやりとりしたかったから川崎の会社にお願いしたけれど、やりとりの大半は作ってくれた音を変えることではなく、いかに良い部分を残しながら必要な部分だけを変えてもらうかに費やした。例えば A面1曲目の Moonglow は、先方が最初にテストカットしてもらったものを何も変えずに採用している。やはりヴァイナルのカッティングにもセッションのようにテイクがあって、テイク1が一番良いというのはここでも結構言えることなのだ。
こうしてできた盤についてはみなさんのご意見ご感想を、たくさんいただきたいところだ。今のところDJする方々からは、僕が若干不安に思っていた「変えなかったところ」に対して肯定的な感想をいただいている。一方で、聴き比べをした敦賀の方々からは「7インチは現場で楽しみたい時、COVERS 2003 は家で聴きたい時」という感想もいただいた。僕自身はというと、敦賀で聴いた時のレコードプレイヤーはとてもシンプルなものであったにも関わらず、7インチとCOVERS 2003との違いが結構思った通りだったので驚いた。その上で、作品というものを違う環境で聴いた時には必ず新しい発見がある。その「思い通り」と「意外」とのバランスこそが、何度やっても予測のつかない、難しく面白い点なのだ。
デジタルに関してはヴァイナルとは全く違う方向性で、2003 年のマスターの音を、極力忠実にマスター化することを目ざした。2003年というのは、DTMの流れの中では「微妙」な年代だ。カセットが宅録の中心機材だった1980年代や、現在アナログ機以上に使われていない「初期」デジタル機材による1990年代(当時は気づかれなかったが、今思うと音の良い機材がたくさんあった)の録音に比べれば十分現在に近づいているが、現在のようにUSB一本で繋げば思った通りのことができるほどパソコン環境は進んでなくて、「Mac博士くん」がネットに書き込む怪しくて細かい情報を探し回ることが必要だった、そんな時期。
その「微妙」さを伝えるため、きちんとしたマスタリングをしていただくことをあえてせず、ほぼ当時のファイルからのコピーをデジタルのマスターにした(それでも自分なりに、音楽的に必要だと思う調整はした)。それで、サブスクの中で他の楽曲との流れで聴くと若干音量が小さく感じられるかもしれない。「CD時代」のような「音圧競争」が意味をなくした今だからこそできる挑戦かもしれないと思っている。
最近若いミュージシャンの方々から、マスタリングについて尋ねられることがよくある。そもそもレコーディングやミックスと同列でマスタリングという作業をとらえること自体どうかと思うし、ヴァイナル盤の場合はマスタリング(カッティング)とプリマスタリング(デジタル同様、入稿する前の音を調整すること)とは違うというのもあるのだけど、一番思うことは、彼らは「プレビュー」できることが当たり前の環境でずっと音楽をやってきたのだなあということだ。
今ならば録音にしてもミックス・マスタリングにしても、録音した音は演奏した瞬間に、(ほぼ)録音した時のままの音で再生できる。テープレコーダーはそうではなくて、録音された音は録音中に聴いているものとは違うのが当たり前で、それがどんな感じであるか、テープを巻き戻して「再生」ボタンを押すまで分からない。レコードのカッティングも、我々にとっては一度カッティングをしてもらい、テストカット盤をプレイヤーにかけるまでどんな音になっているか分からない。その分からない部分を経験によって予測し、必要な調整をしてくださるのが本来の「エンジニア」さんのエンジニアたる部分だし、我々ミュージシャンの方も、演奏した音と再生される音の差をどう「予測」するか、というか、予測が合っても外れてもそれを作品として伝えてゆく腹の座り方が必要だった。演奏された音と再生される音の差を縮めるためにたくさんの努力が払われ、それが今のレコーディング環境に結実しているのだけど、僕はそもそも、純粋な「演奏したそのままの音」というものがあるのか、あってもそれにどんな価値があるのかよく分からないし、むしろ演奏したままの音と再生される音の「差」の部分から見えてくる、演奏者やエンジニアやレーベルスタッフや音楽ファンの時々の好み・気持ちにこそ音楽の面白さがあると思っている。それがなければモータウンもスタジオ・ワンも存在しなかったはずだから。その差を「予測」しながら、演奏→録音→再生→次の演奏…のサイクルをしりとりのように進めてゆくのが僕の好きな音楽の作り方で、最初から最後まで「自分の思う通り」に進めることが一番という考え方とは違うし、「思い通り」に作ることをサポートしてくれるツールにはあまり興味がないかもしれない。
とにかく、ヴァイナルのマスタリングにおいては、DTMプラグインのように自分が変えたいと思ったポイントだけが変わることはありえなくて、しかもそれは基本的には「再生」してみなければ分からないということは押さえておいていいと思う。物理的に針で盤を刻むという作業から出てくる音は、「レコードの音ってアナログでいい感じですねー」などと言った「アナログ」の印象よりもはるかに幅広く、乱暴で、面白い。僕なりの表現で言わせていただくと、流れる時間の感じがまるで違う。ポータブルなプレイヤー、よく調整されたオーディオ、よく調整されてないオーディオ、クラブの大音響、周りの音に消されそうな少音量、環境によって聴こえる音は違っても、良いマスタリングの施されたレコードは、どんな環境でも音楽の伝わるポイントがなくならない。どんな環境でも同じようなスペックで音が出るストリーミングプラットフォームのためのマスタリングはまたそれとは違っていて、そこにはまた別の挑戦もある。それを良いものにしてゆくのに、演奏の場合にもまして、聴く方々の感想が、しかもそれが思いもよらないものであればあるほど、次の作品に活きてくる。みなさまのご意見・ご感想を、常にお待ちしております。

2023.10.11 Wed
エマーソン北村 COVERS 2003 がリリースされました
リリースインフォメーション(ウエブサイト)
https://www.emersonkitamura.com/solo/
release information (website)
https://www.emersonkitamura.com/solo/2023/08/792/
ヴァイナルお取扱店リスト
https://www.emersonkitamura.com/solo/2023/10/807/
デジタル (linkfire)
https://ultravybe.lnk.to/covers2003
bandcamp
https://emersonkitamura.bandcamp.com/album/covers-2003
オフィシャルトレイラー
https://youtu.be/FsUpXOq7pBY
このウェブサイト「Columns」に書いている、COVERS 2003についてのセルフコメント
https://www.emersonkitamura.com/column/2023/09/1019/
まず最初に、オリジナル音源である2003年にリリースされた7インチを買ってくださった皆さんに感謝します。また二十年前、この7インチをきっかけとして僕を初めてライブに呼んでくれた方が何人かいて、その多くは今でも、ライブに呼んでくれてはいろんな話を聞かせてくれます。このお付き合いは何にも代えがたいもので、一番に感謝しています。7インチを持っている方の多くは、自分のコレクションの希少価値が下がるにもかかわらず、COVERS 2003のリリースに対して好意的な反応をしてくれました。 これもありがたいことです。そしてオリジナル音源の再リリースを認めてくれた Small Circle of Friends と当時のスタッフ、今回のリリースに関わったデザイナー、カッティングエンジニア、ディストリビューションスタッフの皆様に感謝します。
来週は二日間に渡ってリリースイベントを行います。ぜひいらしてください!
エマーソン北村 COVERS 2003
リリースイベント 2Days
2023年10月18~19日
Day 1: ライブ at 下北沢 LIVEHAUS
https://forms.gle/zeSBoYhC2BdjJquv5
Day 2: アーティストトーク at 神泉 JULY TREE
https://forms.gle/F6RtMQvC8TFgECxeA