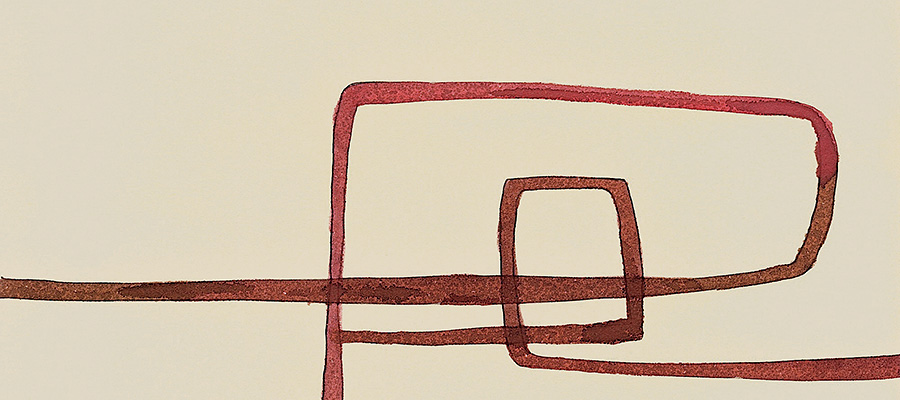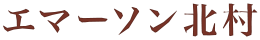em records の江村さんからこの曲のインストカヴァーを作って欲しいと言われたのはかれこれ一年前、2017年の春だった。実際に作業にとりかかったのは秋。
僕も映画「バンコクナイツ」を観た後だったから、二つ返事で引き受けた。しかし実は心の中では微妙なものも感じていた。「今回はアレ、越えられるかなあ……」という不安だ。
「アレ」というのはちょっと上手く言えないのだけど、あえて言葉にすると「非欧米の音楽を、自分が普段頼りにしている欧米ポップスの音楽語彙で制作すること」の微妙さである。
今までも何度か、そのような制作や演奏をしてきた。例えば沖縄、河内音頭、アイヌの音楽。素晴らしいアーティストや仲間のミュージシャンのおかげで、それぞれは楽しかったし、良い物が作れてきたと思う。しかし心の奥ではどこか、これで本当にこの曲の「勘所」をつかんでいるんだろうか、その場所と人に根付いてきた人々の心を分かった内容になっているんだろうかとの不安を、完全にぬぐえないままでもあった。
そもそも僕がレゲエ、アフロなど非西洋のポップスに興味を持つようになったのは、1970年代終わりから80年代頭にかけて起こったパンク・ニューウエーブ、特にイギリスでのそれの影響だった。そこには、アメリカのロックンロールやポップスが大好きなのだが、同時に、アメリカのポップス的な価値観には絶対に取り込まれまいとする強い意志が曲や演奏の端々に表れていた(当時自分がこう言えたわけではないが、その「感じ」だけはちゃんと受け取っていたと思う)。それらの動きがちょっと煮詰まったかな、という感じが出てきたころ、非西洋の要素を取り入れた「ワールドミュージック」がブームになった。その中でよく議論されていたのは「我々はその音楽を新しいと言ってもてはやしているが、それは彼らの音楽を、新たなやり方で搾取しているだけではないか」というものだった。その議論は特に大きな結論を見ないまま、音楽のトレンドの変化にともなって「リスペクトを忘れない」みたいな言葉に置き換わって何となく収まったけど、僕たちにない音楽を、単にアレンジ上の要素として加えるだけのやり方はしたくないという気持ちは残った。
問題は、では「単にアレンジ上の要素で取り込んだ」ものと「本当に相手の音楽を、彼らの気持ちに立って理解したもの」との境目はどこにあるのかということである。これがはっきりしないことによる「もやもや」が、冒頭で言った「アレ」の内容だったのだ。
「田舎はいいね」はリスナーとして聴くと、とてもインパクトがあって楽しい曲だ。しかも、パッと聴くと音楽的にも我々にとってカヴァーしやすい「分かりやすい」曲に思える。ところが僕は、制作者の耳でこれを聴いて、頭をかかえた。この曲のパワーの源がどこから出てくるのか、わからないのだ。「分かりやすい」のはミックス上目に(耳に)つくイントロのフレーズだけで、あとの演奏は非常に混沌としている。例えばもっと「純粋」なモーラムの演奏は、僕らにはまねできないがその演奏内容はとても明確だ。「田舎はいいね」はファンキーなドラムやピアノも入っていて僕らの知っている音楽に近いはずなのに、これを演奏で再現するだけではぜんぜん面白くないものになってしまうのだ。
そこで僕はまず、歌を完コピすることからはじめた。作るのはインストなのに。歌はもちろんお客さんがいちばん良く聴く部分であるが、アレンジと演奏の全体がそれを盛り立てるために向かっていく中心でもある。優秀な人がアレンジと演奏を担当しているならそれは必ず歌を目標にしているはずで、その目標を理解すれば演奏も理解できるのではと思ったからだ。
残念ながらタイ語はひとつもわからない(しかもタイ語というが、ひとつではないそうだ)。しかしそれを音と音程とリズムとで把握することはできる。「どんな音楽も、基本的な要素に分解できないものはない」というのが僕の考えで、例えば譜面に表わせない付点音符と三連符の中間のタイミングも、中間のどこのタイミングで演奏されているかは、譜面に書くのと同様のやり方で把握することができる。それは中途半端な精神論よりも、よっぽど良くその音楽の勘所を自分なりに把握できる方法だと思っている。ただし、コードやタイミングといった「予断」になるようなセオリーはミュートした状態でただ単に耳コピするから、手間はかかる。
こうして莫大な時間をかけて「このタイミングは微妙」という書き込みとカタカナのふりがながびっしり並んだ譜面ができた。
もう一つ、同じ作業をしたパートがある。それはベースだ。
ミックスではあまり良く聴こえないのだけど、「田舎はいいね」を聴き込んでいくうち、この曲の混沌すなわちパワーの源は、ベースにあると思うようになった。ドラムとピアノ、そしてホーンセクションは、欧米ポップスと同じコード解釈でできている。しかしベースは、時にはコードと合わず、かといって「民族音楽的」ではなく、あるきちんとした解釈に沿って演奏されている。
ここで、エマーソンのレゲエ好きが役に立った。ロックバンドなら音が外れていても、レゲエのようなグルーブの中でなら成り立つベースライン、というものがある。そして優秀なベースラインはジャンルを問わず、例えば歌とそれだけを抜き出してみると、音の高低、休符の入れ方などが、きれいに歌と合っているのだ。顔も人生も知らないベーシストの演奏だけど、これはそういうベースであるはずだ。
ピッチが微妙な部分はシンセでは再現できないけど、こうして、曲の頭から最後まで、クラシックのようなベースの譜面もできた(一番二番三番で演奏しているフレーズが違っていた。さすがにこれは踏まえることができなかった)。そして、ひとまずコードのことはあとまわしにして(キーボード奏者なのに……)、延々歌とベースラインのことを考えた。よくある「ロックステディ風トラックの上に、エキゾチックなメロディが乗る」もので済ませたくなかった。逆なのだ。ロックステディがその現場でやっていた、音楽要素のミックスの作業を、楽曲に即して再度ここで実行する。その結果は単なるロックステディ風にはならないはずだ。実家にあるヤマハの1970年代製エレクトーンからサンプリングしてきたリズムボックスを延々ながしながら。
ここまでが「田舎はいいね」に僕が費やした時間の、7割ほどである。コードも印象的なイントロフレーズも大切だが、それは気合いを入れて何テイクもかけないようにすれば、きっと良くなる。ライブでも、右手はメロ/左手はベースを同時に弾くことになるから、左手と右手のシャッフル度合い(付点音符と三連符の中間の、タイミングの傾き)がそれぞれ異なって難しいが、それを何となくひとつのパターンにそろえてしまっては、原曲の何か大事な部分をなくしてしまう。
「田舎はいいね」の混沌は、ざっくりいうと、アメリカのロックやポップスが好きで、新しくて楽しいことがやりたい気持ちと、それに捕われてたまるか、自分たちの音楽を作るんだという気概とのぶつかり合いから生まれる、混沌だった。それが演奏上で最も顕著にあらわれていたのがベース。ベースって、そういうパートなのだ。田舎はいいねのベースは、見事にそのぶつかりあいに勝っている。
制作途中に気持ちが煮詰まって、江村氏に相談したことがあった。そのとき江村氏は「パッタナー」という言葉をあげて、まさにこのようなことが1970年代前後のタイのプロデューサーの間で目指されていたことを教えてくれた。ならば僕も、自分のパッタナーをするつもりでこの曲に取り組めばいいのだと、目の前がパッと開けた気持ちがしたのだった。
もうひとつ、最も大事なことを言うと、「田舎はいいね」の歌詞とタイトルは、単に田舎を賛美するものではないそうだ。当時のタイではたくさんの人が経済的な理由から住み慣れた土地を離れ、都会に出て行った。都会で働き、田舎との格差から生まれる問題に疲れた心(先日のタイ爆音映画祭でも繰り返し繰り返し扱われていたテーマだった)にマッチするよう、生まれたのがこの曲だということだ。だから「田舎はいいね」と歌っていても、心はぜんぜんその通りではないのだ。良い歌ってそういうことですよね。これで言葉が分かったら最高なのだけど……