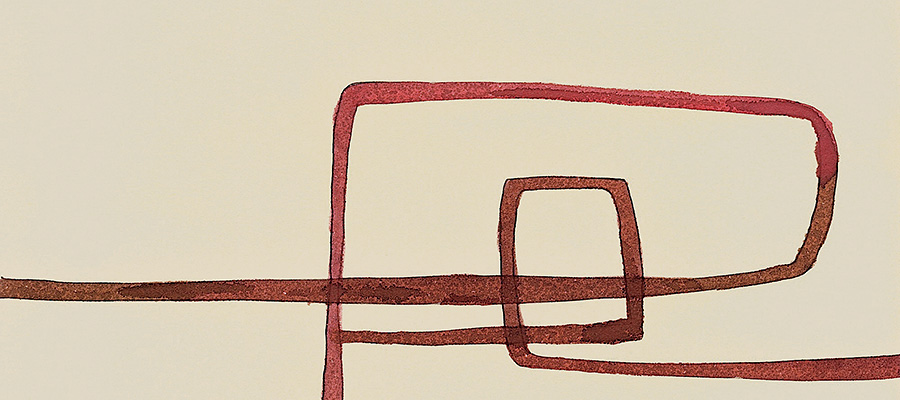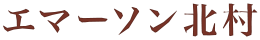B1 (デジタルでは4曲目) You’ll Never Find (Kenneth Gamble, Leon A. Huff)
JAGATARAのベーシストで尊敬する友達でもあったNABEちゃんが「俺はねえ、初めて買ったLPは必ずB面からかけるんだよ〜」と言っていたのにならって、ヴァイナルをまとめる作業はいつもB面から始めることにしている。なのでカヴァーの元曲を紹介するのもこのトラックから。
COVERS 2003には、ジャッキー・ミットーのような演奏をストレートにやりたいと思って選んだ曲と、表面上はレゲエでなくても姿勢は彼らのやり方にのっとってやろうとした曲との2タイプが、ちょうど半分ずつ収録されている。この曲はあきらかに前者で、ジャッキー・ミットーのアルバムThe Keyboard Kingで僕がはじめて聴いたこの曲のアレンジをお手本にしている。
ミットーのトラックそのものがカヴァーで、オリジナルはギャンブル・ハフのソングライティングチームが作曲してルー・ロウルズが歌ったソウル・チューン、1976年のYou’ll Never Find Another Love like Mineだ。ミットーのヴァージョンは、レゲエシンガーのJohn Holtによるカヴァーのためにバニー・リーのプロダクションで彼達が演奏した音源から、レゲエではしごく普通のことだけど、リズムトラックだけを再使用して自分のオルガンを重ねている(ヴォーカルもダブ要素として登場している)。つまり僕のトラックは、USで制作されたソウル→のレゲエシンガーのカヴァー→のオルガンヴァージョン→をカヴァーした、四代目?のヴァージョンとなる。
この曲をとりあげようと思った理由は、その「レゲエらしくないのにレゲエ以外の何物でもない」グルーヴだ。スライ・ダンバーのシンコペーションばかりのドラムフレーズと、ロビー・シェイクスピアの、コードのメジャー7th音(コードのルートからドレミファソラシと数えたときのシ)から始まるベースラインという、普通なら避けるべきことだらけの演奏なのに、全体としては見事に成り立っている不思議なリズムアレンジ。しかもそのリズム・コード共にモヤがかかったような雰囲気から生まれるグルーヴは強くしなやかで、原曲のフィリー・ソウルよりもバネがある。ジャッキー・ミットーのオルガンも、それだけを取り出して聴けばまったくイージーリスニングというか、この時代によくあるポップスのオルガン演奏なのに、リズム隊と一緒になるとたちまちグルーヴを発揮する。このオルガンと他のオルガンの違いは何なのか、2000年代ならば「音色」と答える人もあっただろうが僕はそう思わない。伸ばす音と短く切る音の配置とタイミング、そして原曲の歌のようなそうでないような微妙なメロディ、つまりはジャッキー・ミットー自身の「音符」そのものが、ドラムアンドベースと一緒になった時に他にはないグルーヴを生み出しているのだ。おそらく全員が同時代のUSのソウルやファンクの演奏をタイムラグなしで身につけているはず。そこから出てくるファンクのエッセンスが、ワンドロップなどひとつもないのにレゲエでしかないグルーヴを感じさせるということが、ヒップホップも4つ打ちもなかった時代の十六分音符の演奏の凄みと幅広さを表わしている。
この雰囲気を何とか自分のものにしたい、という極めてストレートな気持ちで取り組んだのだけど、やり方がストレートすぎて、足鍵盤とメロディの音域が重なっても気にしてなかったり、普通ならもっと分かりやすくすべき工夫をまったくしなかったので、聴こえてくる演奏はまったくストレートではなくなってしまった。リズムマシンTR-808のフレーズだけは少し整理しているのだけど、その方向性には僕の1980年代ニューウエーブから1990年代にかけての感覚がうかがわれる。この傾向はCOVERS 2003の全体にあって、収録曲のアレンジから「時代感」を感じるとしたらまず打ち込みドラムのパターン(だけ)ではないかと思う。ドラムのフレーズというものはそういう風に手がかりとされがちなので、ちょっと可哀想だ。それなら、大好きなピューンというシンドラも入れておけばよかった。
ヴァイナルのマスタリングでは、とにかくキックに注目して全体の感じを決めていった。強く、しかし、ローエンドが出すぎて重くならないように。重さは足鍵盤に担当させて、バネを持って音楽を進めてくれるように。イントロの二発のキックとシンバルだけで(TR-808ではこういうイントロが作れる)、続くB面のすべての音をうまく導いてくれるようにと願って作った。

Jackie Mittoo The Keyboard King
https://www.discogs.com/release/2388181-Jackie-Mitto-The-Keyboard-King