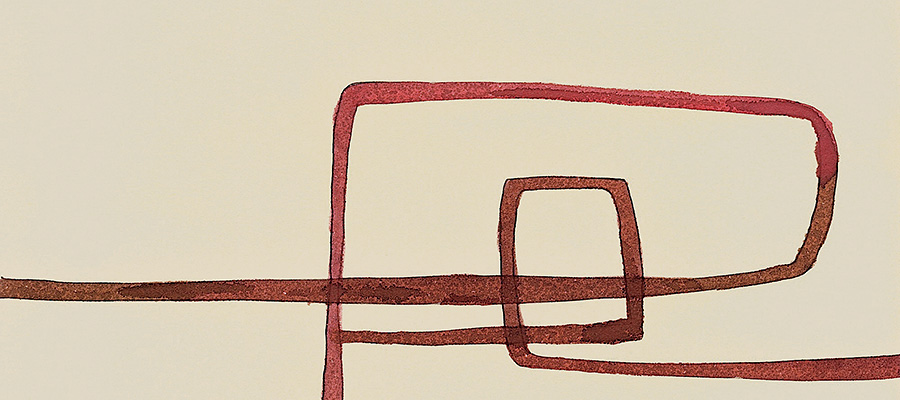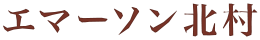COVERS 2003 A1 Moonglow (Will Hudson-Eddie DeLange-Irving Mills)
オリジナルの7インチでもCOVERS 2003でも冒頭のトラックとなったこの曲が、一番、カヴァー元と自分のヴァージョンの距離があるかもしれない。僕がこの曲を始めて聴いたのは1970年代にいたるところに存在した「魅惑のスクリーンミュージック」的なLPの一枚で、「ピクニック」という映画のサウンドトラックとしてだった(映画は観たことがない)。熱を出して学校を休んだ昼などによく聴いていたのだけど、ゴージャスな(と当時は思った)映画音楽が並ぶ中でこの曲になると急に音にスキマができて、そのツーンとした雰囲気が好きだった。後になって、この曲は映画よりさらに以前、スイングジャズの時代に作られたということを知った。
この曲をスタンダードにしたのは何といってもベニー・グッドマンの演奏によるだろう。僕は特に、彼がテディ・ウィルソンとジーン・クルーパのトリオにライオネル・ハンプトンを加えて録音したスモール・グループの音源が好きだ。このグループはメインであるビッグバンドの幕間用編成にもかかわらず「進んだ」バンドであった、というのがジャズ界での評価らしい。僕の感覚で聴くと、このバンドの人間関係はすごく今のロックバンドに近かったのではないかと想像してしまう。パッと聴きは調和していて優美なのに、いつもどこか緊張をはらんでいる。四人という数も絶妙。そして僕がとにかく好きなライオネル・ハンプトンのヴィブラフォンが素晴らしい。
ベニー・グッドマンのヴァージョンと僕のヴァージョンの間には、それらとは全然似ていない、でもこれも素晴らしいヴァージョンが挟まっている。1960年代に盛り上がったグルーヴィなオルガンジャズのプレイヤー、ジミー・マグリフの演奏だ。踊るための音楽で、ジュークボックスでかけられることを前提としたレコードを数多く作ったGroove Merchantというレーベルのアーティストの中でも、オルガンという楽器を一番上手に活かした人。もちろんリズムはファンクなのだけど、コード進行のアレンジが他にはない四度シャープから半音ずつ降りてゆく(階名で読むとファ#→ファ→ミ→レ……)、それだけを取り出すと静謐とも言える進行で、これと強いグルーヴを組み合わせるというアイデアは、僕もしっかり影響を受けている。数ある音楽スタイルの中で「何を」やるかということは僕にとってはあまり大事でなくて、スタイルを構成する音楽要素にまでさかのぼった時にそれを「どう」表すか、にアレンジの面白さはあると思っている。大抵こんがらがってしまうけど。
ドラムボックスのフレーズは込み入ったオルガンのアレンジとは逆に、はっきりとRhythm & Sound的なダブ・テクノの影響が分かる。やっぱり時代感がここに現れている。冒頭からずっと聴こえる低い音は、ローランドのSystem 100というシンセ。もう40数年使っている。