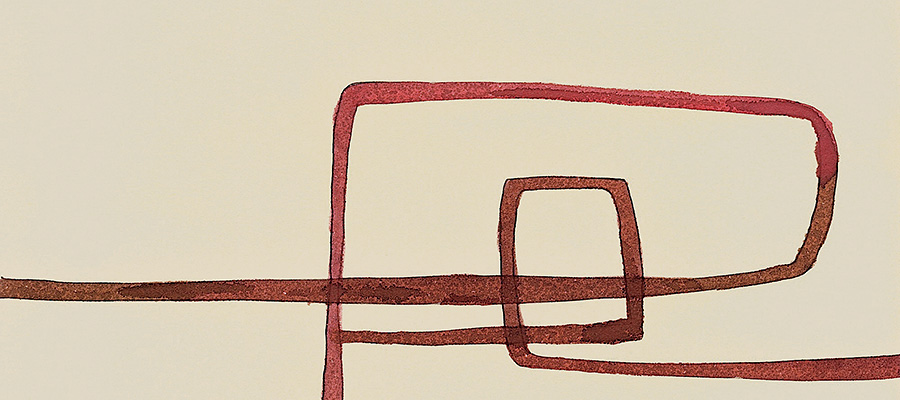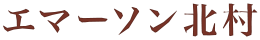COVERS 2003 A3 Ram Jam (Jackie Mittoo, C. S. Dodd)
カヴァー曲紹介も最後になり、ついにRam Jamを取り上げる時が来た。いうまでもなくジャッキー・ミットーの最も有名で、いちばんシンプルだけど一番さまざまな気分が盛り込まれている曲。MUTE BEATでの僕の先任のキーボーディスト、朝本浩文さんのユニット名にもありました。
シンプルという印象に反して、やってみると意外に難しい曲。いや、単にやるだけならシンプルなのだけど、曲を自分のものにしようとするとたくさん「?」な点が出てきて、大事なところはその間からすり抜けてしまう。例えばコード。主メロである和音と、伴奏を構成するコード進行の和音とが一致しない。不協和音ではないけれど、主メロとコード進行との費やす時間がずれていて、バンドでなら気にならないのだけど一人だと意外に悩んでしまう。COVERS 2003の僕の演奏はそこがオリジナルと違うのだけど、気がつくだろうか?ロックステディを代表すると思われているベースラインにしても、かつて一度、リロイ・シブルス(ヘプトーンズのヴォーカリストだがスタジオ・ワンのベーシストでもあり、多数の有名トラックのベースを担当してきた)がこの曲のベースラインを説明する、という夢のようなシーンに出くわしたことがあるのだが、思っていたのとは違うなんだかふんわりした話で終わって、拍子抜けしたことがある。僕はUSで活動してきたミュージシャンがするような「俺の作ったこのフレーズはこう弾くのが肝心で……」のような説明を期待していたのだと思うけど、きっと彼のミュージシャンシップはそういう部分にはないのだろう。
だからといって、レゲエが不明確なところの多い、いい加減な音楽だとは思わない。いや、不明確なところは多いのだけど、それを僕ら(元からその音楽を担っているわけではない)演奏者の都合で「ここはいい加減に」と済ませてしまっては、肝心のフレーズの「強度」はいつまでたっても生まれないのではないかな。多少面倒に思われようとも「ここのコードは何なんすかー、このリズムはどうなってるんですか?」とあくまで音楽的に自分のものにしようとすることでしか、人に伝わるものを作れるようにならないのではと思っている。それが結果的にレゲエにジャンル分けされようがされまいが。
何度かトークイベントでも話して、このセルフコメントでも(9)に登場しているJackie Mittoo at Home and Abroadという論文では、Ram Jamが1950~60年代に流行したキューバ音楽をモチーフにしたポップス曲、Poincianaをリユースしていると述べられているのだけど、PoincianaのどこがRam Jamにリユースされているのか、僕はいまだに分かっていない。多分、USのピアニストであるアーマッド・ジャマル(2023年に亡くなりました)がライヴ盤に残している演奏の冒頭部分のことではないかと思うのだけど、ただはっきりと分からなくても、Poincianaの、そして多分アーマッド・ジャマルの、柔らかいがはっきりしたグルーヴの中からさまざまな色彩が浮かんでくるような「雰囲気」は確かにミットーに受け継がれていて、そこにロックな世代の気分とシンプルさが付け加えられてRam Jamとして形をなした、と想像することもできるだろう。音楽と音楽のつながりにおいてこういう「雰囲気」は決して(コードのように)不明確なものではなくて、ちゃんと、ミュージシャンがイメージして形にできるはずのものだ……余分なことに気をとられなければ。
想像ついでに。上記の論文で僕が初めて知ったことの一つに、ジャッキー・ミットーが子供のころ学校の催しでピアノを弾いたことがあり、その時の曲は当時の映画音楽Theme From A Summer Placeだったという話がある。この曲は後にTan Tan (EddieThornton)やMUTE BEATもレパートリーにしたレゲエで最も多くカヴァーされる曲のひとつだけど、そのはるか以前にミットーが弾いていたというエピソードは、なぜか僕に強いイメージを与える。この曲やPoincianaにはなにか、目に見えるものからほんの少し先が透けているような、ちょっとだけ非現実的な感じがある。それを弾いていたミットーがミュージシャンになって生み出したのは、外でもない現実を生きる人のための音楽であるスカやロックステディ、そしてレゲエだった。だけど自分が作曲する時には、どこかで常に、昔自分が弾いたイージーリスニングのような、ちょっと非現実感な何かもいっしょに抱いていたのではないかな。ミットーの演奏を聴くと僕はいつもそんな感じがする。