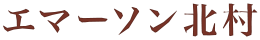アルバムの終り方で好きなものは細野晴臣さんの「はらいそ」。足音を立てて去りかけた細野さんが急いで戻ってきては「次はモアベターよ!」と宣言する。
上野の両大師橋、今は何の変哲もない橋だけど、昭和戦前に桑原甲子雄さんは自分の家の近くのこの橋でたくさんの写真を撮っている。そもそもは「一銭五厘たちの横丁」という本がきっかけだった。戦前の上野で暮らしていた人々の記念写真のその後を追うことで、その後彼らが体験する戦争と空襲の歴史を丁寧に描いて、声高に訴える部分はまったくないのに反戦の意志がしっかり伝わってくる、すばらしい本だった。その写真が桑原さんのもので、そこからご本人の写真集へと進み、犬を散歩させている子供の写真に自分の影が移り込んでいるカットに出会ったのだった(桑原さんの写真の中では、とりたてて有名ではないのかも知れない。近年出版された写真集にこの写真は収録されていない)。
で、音楽のこと。「イチ・ロク・ニ・ゴー」という基本中の基本のコード進行と自分が一番好きなシャッフルスカのビートで曲を作るという、ある意味危険きわまりないことをやったわけだ。キセル兄と話したこともあるけど、シンプルなモノには惹かれるだけに、どんなオルタナな音楽を作るよりも難しい部分があるのだ。リズムマシンにはスカのパターンはやらせず、Roland System 100 で作った、シンセ的には一分で作れる「ピュン」音だけに電子音楽の心意気をこめて、トラックを作った。
自分にはどうしても整理してしまうクセがあり、正しいコードの音、正しいタイミングのリズムにメロディーも演奏も押し込めてしまうところがある。本当はもっとグダグダで、自分勝手で人に迷惑もかけ、わーっと泣いたり怒ったりする気持ちを表したいのだが、できあがるとなぜか折り目正しくなっている。まあでもそこも自分なのかなあとも思う。センエツながら桑原さんの写真が好きな理由もそこだし。
ネタをひとつばらします。エンディングのベースラインは、松永さんがリハの休憩時間などでよく弾いていたフレーズ。元は ink spots なのか何なのか、ニヤニヤしながらブルースやこういった小唄系の、楽器を始めた初日にコピーするようなフレーズをギャグとして演奏していたが、実はすごく良い音だったのだ。それを曲に折り込むという私情?をはさませてもらって、アルバムを終えました。
先日渋谷クアトロのリリースイベントでは、スガちゃん(菅沼雄太)に言わせると「人力では無理な、中途半端なテンポ」らしいこの曲(ホメてくれてるんだと思う)に、お客さんは手拍子をしてくれました。そのビートに送られて松永さんは足音を立てて去り、えーっと、どうやって戻ってくるのでしょうか。やっぱり僕らも「次はモアベターよ」と言い続けなければならないのです、きっと。
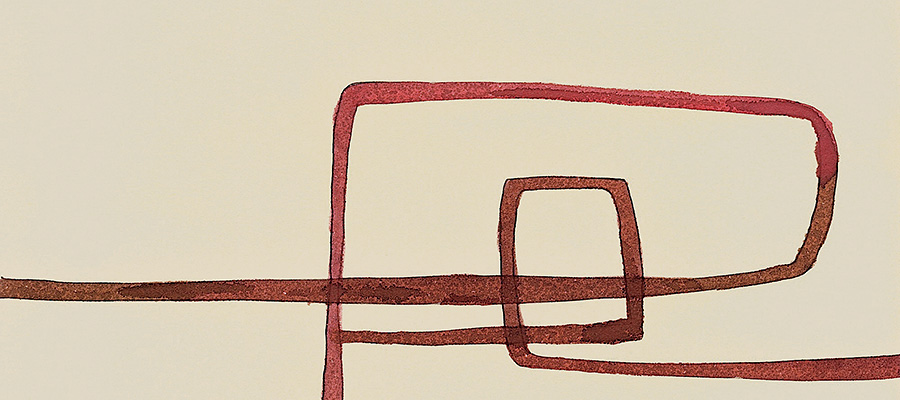
Emerson Kitamura
Column
2014.10.31 Fri
コメンタリー: 14. 両大師橋の犬
2014.09.13 Sat
コメンタリー: 13. 夜中
こんばんは。秋らしくなってきましたね。
この全曲コメンタリーもかなりの所まで来た。このコラムはマニアック解禁にしているので読みづらい方には申し訳ないと思っているが、「読んでます」と感想を下さる方もいて、力づけられる。ありがとうございます。
普段は「自分はオルガンプレイヤーすから」とピアノにはあまり興味ないふりをしているが、実は、ピアノ、すごく好きだ。人から習ったことがないことでどことなく引け目を感じているが、高校生のころはピアノのあるところに行って個人練していたこともある。
その頃どんなのが好きだったかと言うと、モンクは別格として、ダラー・ブランド(アブドゥーラ・イブラヒム)の African Piano。練習したな。実はいわゆるワールド・ミュージックへの接近ルートとして、パンク→レゲエという道のりの他に、このような(オルタナティブな)ジャズ→各国音楽、というルートも、自分にはある。むしろこっちの方が自分にとっては古く、より自分自身に近かったりする。
でも、「夜中」のような曲の方が、スリーコード・定型小節数のロックよりも、曲にかかってくる重層性という点では、簡単だとも言える。いろんな人がいろんなトライを重ねてきたポップやロックにそのフォーマットでもう一曲足すことの方が、フォーマットから「自由」になった曲を作るよりも、闘わなければならない相手の蓄積は余程大きく、むづかしい。
それでもね、出ちゃうんだこういう曲が。モンクの「Crepuscule with Nellie」には遠く及ばないが、そういうボローンとした、暖かくかつ空虚、みたいなものは、どうしても基本にある。そして僕の場合は、ピアノにローランドの System 100(Mじゃない) を足したくなる。この二つこそ、僕にとっては「最高のテクノ楽器」だからだ。あ、KORG のアナログディレイも。
曲後半の部分は、何度も試しているリフの、一断片。「遠近(おちこち)に」初回特典の「エマソロ・ライブサンプラー」に収録されているパリのカフェでのインプロも、その一つのバリエーション。今回アルバムではインプロを収録するという発想を捨てたため譜面で書ける内容になっているが、ライブにはこれとは別のオチの付け方があるはずと、思っている。
2014.09.09 Tue
コメンタリー: 12. I’ve Grown Accustomed to Her Face
アルバムを作っている時は後半の曲が地味かなあ〜と思っていたのだが、自分の周りの感想では後半の評価が高い。ありがたいことだが、こういうことは絶対に自分一人では予想できないなあ〜。
エマソロの楽器には二種類のパターンがあって、今では YAMAHA DX100 というミニシンセでライブすることも多くなったが元々はオルガンを弾くのがエマソロだった(だからDX100も2台並べている)。アルバムも初期には全曲オルガンでいこうと思っていた。この曲はその時期に録ったものでアルバム中最も古く、2009年の夏。シアターイワトは劇団黒テント(高校生の頃観てた)が拠点として維持していた劇場で、以前は多分倉庫か商家だったものを改造したのだと思う。かねてから自分の理想のスタジオというのがあって、それはあまり創作の場っていう感じがなくて、地元の商店やら町工場みたいな場所というイメージなので、ぴったりだったのだ。実際録ってみると残響の多さに苦労したが、それもそもそも狙っていたことなので、録れたものを落ち着いて聴いてみて、これでいいじゃんということになった。この曲はミックスすらしていない。ラフミックスそのままで、どうしてもこれを超えるミックスが作れなかったのだ。
親の話では6才ころ、楽器店のショーウインドウにあったヤマハエレクトーンに触りたがったというのが、僕のオルガン歴の始まりだ。エマソロのイージーリスニング感はそこから生まれているから、オルガンにしてもジミー・スミスやキース・エマーソン(笑)のようなゴリっとしたものよりもビル・ドゲットやワイルド・ビル・デイビスのようなイナタイもの、あるいはルー・ベネットやローダ・スコットのフランス録音のような、手回しオルガンからの連続をちゃんと感じられる音の方が好きだ。(一番好きなオルガンプレイヤーはフランスのエディ・ルイスだがその話はまた別に)それで「ステレオでなくモノ」「部屋鳴りによるリバーブ」という、この曲の録音方針ができた。一見逆のようだが、僕はオルガンには機種のこだわりが全くない。つきつめればオルガンはサイン派発生器の集合体、ある意味では最高のテクノ楽器だと思っているので、例えば逆に DX7 は立派にオルガンだと思っている。楽器の音色自体には情感が乏しくて、そんな音色で情感を出せる演奏をすること、なぜかそこにはこだわりを持っている。さらに、そのことを、神楽坂の元倉庫の劇場で録りたかったのだ。こだわってるのかこだわってないのか、自分でもめんどくさいな〜と思う…
アルバムレコーディングの後半になって、もう何度かシアターイワトを使わせていただいたいと思ったがその時にはもうなかった。でも平野さん、ありがとうございました。
それで、曲のこと。ミュージカル映画は大好きだがこの曲が入っている「マイ・フェア・レディ」はそんなに好きではない。斉藤和義さんのコメントにもあるように、ウエス・モンゴメリーのライブアルバム「Full house」収録曲の方がきっかけだ。実はいろんなアレンジでずっとやっていて、いつまでたってもベストのアレンジが見つからなかった。ここでひとつの結果を見たような気がするが、それは一番「普通のオルガン演奏をする」というものだった。

2014.09.04 Thu
コメンタリー: 11. 橋からの眺め
古今東西南北、橋を題材にした曲は多いですね。スカの名曲 Bridge View(これは地名だと思う)、キンクスは Waterloo Sunset、A View from the Bridge なんてのもある。大体僕も含めて人はやりきれなくなると橋のところをぶらぶらするようで、そんな「橋」ソングの系譜にこの曲は入れてもらえるのだろうか …
レゲエもブルースも好きだけど、音の構造にはずいぶん違いがある。表わしている気持ちには共通するものを感じても、それを成り立たせている勘どころはたまに正反対な場合すらある。特に、レゲエに特有の「ど」マイナーキーによるブルース感覚、みたいのは、メジャーキーのポップソングが好きな北村にとっては扱いの難しいものだ。Taj Mahal を聴くとそれがいとも簡単に超えられているのに感激するのだけど、聴くとやるとは大違いで、Taj Mahal がさらっとそういうことをやっているから自分もそういう曲を作れるような気になると、めちゃめちゃ苦労することになる。… みたいなことがこの曲を作っていた時に思ったことだった。
でも、意外にこの曲は「育った」かもしれない。北海道 RSR フェスの草むらで、大阪カレー屋のちゃぶ台の上で、演奏した時の何かを、曲の方も吸い取って帰ってきているのかもしれない。
この曲の録音は今はなき神楽坂の「シアターイワト」で録らせてもらった(神保町「スタジオイワト」さんとは別)。時期もこのアルバムの中では次の曲、Accustomed に次いで古い時期に録音した。ミックスもアルバム中で一番早く、テスト的にミックスしたものをそのまま使った。なので録れた音はいろいろでこぼこしていたのだが、m’s disk 滝瀬さんのマスタリングを施された瞬間に、何かが完成した。滝瀬さんの話では、既にぎっしりと詰め込まれ、低音も高音もトリートされ尽くしたミックスよりも、でこぼこの残っているものの方がやり易いそうだ。その、パッと拡らける感じは「知らない家」の次に合うかも、と思って、試しにやってみたら、予想以上の感じがあった(当初は別の曲順にする予定だった)。まあもちろん「知らない家」で橋まで行ったから、次はそこから眺める、というのもある。
こういうことは、良くなかったことよりももっと、覚えておくべきことなのだろうが、それを次に活かすことは、反省することよりも難しいね。
2014.09.01 Mon
コメンタリー: 10. 知らない家
この曲のことは「遠近(おちこち)に」オフィシャルリーフレットにも書いているので、それにないことを少し。
元々言葉関係の表現は好きだが、自分でやるつもりなどさらさらなかった。今回のアルバムには最初からゲストを一切入れないつもりだったが一つだけずっと入れたいと思っていたものがあって、それは ECD のラップというか声だった。
さすがに歌詞まで丸投げするわけには行かないから、自分で書くしかない。友人の Manuel Bienvenu に「Good Luck Mr. Gorbachev」というリーディングの曲があり、こういうテイストを目指すなら歌詞を書くのもアリかと思った。
高野文子さんのマンガ「るきさん」に、自転車に乗っていて落としたせんべいのことを、自分にとってはすぐ近くだが「せんべいにとってはかなりの距離だ」と思いを馳せるシーンがある。そのセリフがなぜか自分の中の口癖のようになっていて、「A にとっては○○だが、B にとっては結構な距離だ」という A と B の組み合わせをいろいろ考えてみようというのがこの曲の歌詞の出発点だった。
そうしてできた歌詞をとりあえず自分の声で録音し、デモを ECD さんに聴かせたら「僕がやることには問題ないが、これは絶対北村がやった方が良い」と言って頑として譲らず、結局自分がやることになった。
これが自分でもまさかのリーディングをやることになった経緯だが、でもこの曲で本当にコメンタリーしたいことは歌詞ではなく音楽の方。リズムマシン 808 の「カウベル」の音色はヤン富田さんのジョンケージカヴァー「4分33秒」を待つまでもなく、自分にはこの音色を使う器がないと(笑)エマソロでは一切使わなかったのだけどついに使ってしまった。もはやそういうこだわりもどうでも良くなってきた … みたいなこと。
また意外にこの曲でかんばったつもりなのは、曲のコード感。もちろん、ロバートワイアットの「muddy mouth」に影響を受けている。
自分ではこの曲はレゲエのトースティングだと思っているので、バックトラック+リーディングという関係ではなく、声がなくても成り立つ曲にリーディングを足している形にしたつもりだ。先月(2014年8月)北海道ライジングサンからこの曲を(弾きながら語るという方法で)ライブで演奏し始めた。しっかり声を出しながらもどこかトラックに埋没する気持ちで、と、やりながら考えていることは普段楽器を演奏する時と意外に変わらないものだ、ということを始めて体験した。
2014.08.26 Tue
コメンタリー: 9. ニワ
YOSSY Little Noise Weaver がものすごく良い、そして、曲の感じをすごく生かしたカバーをやってくれているのだ!YLNW / Tucker / エマーソンのライブではそうやって、互いの曲をカバーし合ったり参加し合ったり、有機的な音楽作りをしています。観て下さいね。
で、ニワというのは商家の表と裏をつなぐ土間のことで、生涯かけて日本人の住み方の膨大な記録を取った西山夘三さんの本にあって … みたいな話はまた MC に取っといて、ブライアン・イーノは、きっちりアンビエントしちゃう前の「Another Green World」くらいが一番好きなんすよー、という話。
エマソロの電子音楽度合いというのははなはだ中途半端なんだけど、実はアルバムを作るにあたっては、パッチシンセで延々インプロなんてのも録ってあったりする。結局それらを使わなかったのは、そういったテクノ通過後の電子音楽が持つ「自由」よりも、初期のシンセ音楽家達が譜面に書いた一音一音をシーケンサーに起こしてゆくような「不自由」さの方に、電子音楽の醍醐味を感じてしまうからなのだ。テクノ後のシンセ音楽で好きなのは Matmos の supreme balloon くらいかなあ。本当に「遠近(おちこち)に」の全体を通して、当初予想したよりもインプロや一期一会の要素は 少なくなった。ひょっとしたら、自分の力を出し切れない、こじんまりとしたアルバムになってしまっているのではないかと思うこともあった。本当のところはわからず、皆さんの感想を待つのみだが、今自分が一番心の動くやり方はインプロではなかった、としか言いようがない。
その代わり、ロングトーンのコードをシンセの VCA でゲートのように切る、と言った手間のかかる方法は使っている。僕らの世代のトラックメイカーでも、コンプのゲートでリフを作るくらいのことは、みんなやっていたのだ。
まあ言ったら、その方が「ニワ」(箱庭)な感じに、なるでしょ?
僕は超常現象は一切信じないが、子供のころ実家の店でぼんやりしていると、ニワの隅っこにはいろんな不思議なものが生きている気がしたものだ。電子音楽も、電子音に住むムクムクした命を見つけ出す作業。アンビエントだの感覚の拡大だのには興味がないが、その程度には、不思議なことを信じてる。
この曲におけるミックス: そんな曲でも、ベースはレゲエファウンデーションの「General」的なラインを織り込んでます!
2014.08.26 Tue
コメンタリー: 8. 王冠
ライジングのために帰った実家で、残してあるエレクトーンに触っていた。そうこのエレクトーンについているリズムボックスは既にサンプリングしてあって、「王冠」に使ったんだった。普段あまりにワングルーブの曲が多いので、JAGATARA じゃないけれど、ワングルーブだけどキメがあって、展開があって、という曲を作りたかったのだ。でも、リフの絡みでリズムを作る演奏は詰めてゆくとどうしてもクールになってゆくな、一人でもバンドでも。まあもともとこの曲のグルーブのイメージはちょっとバーチャルというか、エレクトーンを弾くアフリカ人アーティスト、フランシス・ベベイのように、自らを客観的に見た上で作っているグルーブというところがあるから、バンドで人間が産むグルーブとはちょっと違う感じに仕上がってもいいのかも知れない。だから、トーキング・ヘッズとか今でも有効なわけだよな。イミテーションの宝石が散りばめられた王冠のような ..,
と、いうようなことを制作時には考えていたことを、実家のエレクトーンに座りながら、思い出した。
まあそんなことを抜きにしても、かなり変わった制作方法で作っていることは間違いない。楽器のクレジットは、お客さんに手の内を見せるのは失礼という発想からしなかったけど、アルバム中でこの曲のみ YC-10、エゴラッピンの録音でも多用しているオルガン。個人的に好きなのは 808 のコンガの八分連打、で確か、808 の信号でサンプラーを鳴らすという、アナログの極みな方法でトラックを作ったと思う。アレシスのリズム音源をアナログ→MIDI の逆変換機として使えば、できるのだ。
というマニアックな話で終わってすいません。とにかく、コンピュータ上で揃えて完成、という作り方は、一曲もしていないのです。それはバンドのない自分の、せめてもの「熱」をこめるやり方なのです。
2014.08.21 Thu
エマーソン北村の誕生
藤川毅さんから、アルバム「遠近(おちこち)に」へのコメントをいただきました。と思ったらこれが素晴らしい!僕が自分から一度もまとめて公にしなかったインディーレーベル「ナツメグ」と「エマーソン」という名前との関係やそこでの僕(と藤川さん)の仕事について、本人以上によくまとめてくれてます!
最後はアルバムのことになってゆくのですが、この「コラム」コーナーの楽曲コメンタリーも丁度A面の終わりまで来たし、ゆっくり読んで欲しいのでここに載せます。僕が勝手に「エマーソン北村の誕生」というタイトルをつけました。藤川さんありがとうございました。以下本文
北村さんとの出会いは四半世紀以上さかのぼったある日のことです。
実は同じ職場で働いていました。
北村さんはライヴハウスを運営する部門でエンジニアをされたりライヴハウスの現場で働いておられました。一方でミュート・ビートやJAGATARAのメンバーとしても活躍されていました。
僕は、その会社が、雑誌をつくろうとしていた時のスタッフとして働いていたのですが、雑誌計画が頓挫したことにより、そこが始動させつつあったレーベル運営を手伝うことになりました。
レーベルの第一弾はピアニカ前田さんの「Just You Just Me」という7インチシングルでした。88年頃のことですが、実はその頃、ピアニカ前田さんはまだピアニカ前田という名前になっていなくてそのシングルで正式にピアニカ前田という名前になりました。一時期はピラニア前田にしようなどという話もありました。
北村さんや僕が働いていた会社のボスはとても面白い人で、何でも面白がっるところがあって、それがその会社の大きな原動力でした。ピアニカ前田さんを皮切りに、さかな、のなか悟空&人間国宝、苔のむすまで、フェダインといった初期のレーベルの顔ぶれも相当なものですが、コレ以降はレゲエやヒップホップやクラブ系のアーティスト、ピアニカ前田さんのシングルでもサウンドをしきっていた松竹谷清さん率いるトマトス、世界最大のジャケットを作ってしまい納品に難儀した遠藤賢司さん…それ以外にも本当にたくさんのアーティストを手がけました。
レーベルのサウンドとしてのカラーはバラバラだったかもしれませんが、レーベルのポリシーは、「面白いものは面白がって、何でも自分たちでやってみよう!」ということに尽きるような気がします。
北村さんは最初こそライヴハウスのスタッフでしたが、レーベルが立ち上がってからはレーベルの仕事も演奏はもちろん、エンジニア、アレンジャー、プロデューサーとして活躍されました。その頃の僕らにレーベル運営や音源制作のノウハウがふんだんにあったかというとそうではなかったのですが、知り合いなどから情報を得たりしつつ、とにかく自分たちでやったレーベルでした。
そんなレーベルから北村さんのシングルを出そうということになりました。会社のボスが「北村さんになんか出来ないすか? デモ作ってみてくんせー」といったのだと思います。それに対して上がってきた音が面白いものだったので7インチでリリースしようということになります。
そこで問題になったのが北村さんのアーティスト名をどうするか? ということです。じつは、このアーティスト名をどうするか? については、北村さんは関わっていなかったように記憶しています。会社のボスが「鍵盤弾きって言うとやっぱ有名なのはエマーソン・レイク&パーマーのキース・エマーソンっすよねー。だからキース・エマーソンから名前もらってエマーソン北村でいくっす」と勝手に決めちゃったのです。北村さんの本名は北村賢治ですから、キース・エマーソンから名前をもらうとしてもキース北村か賢治エマーソンのはずなのですが、そんなことはお構いなしに、勝手にエマーソン北村になっちゃったのです。ひどい話です。
ボスから、「藤川さん、エマーソンのプレス・リリース作ってくんせー。キース・エマーソンがでっかいシンセ弾いてる写真と北村さんの顔写真合成できないっすか?」というので、スキャナーで写真を読み込んで作りましたよ。それ以降は、北村さんは嫌がる素振りも見せずエマーソン北村です。
エマーソン北村として、自身のいくつかのソロ作や数多くのセッション参加を重ね、その知名度は僕がここで説明するまでもないわけですが、僕が今回くどくどと昔話をしたのには、北村さんの新作「遠近に」を聴いて、僕らが働いていたレーベル、ナツメグでの「面白いものは面白がって、何でも自分たちでやってみよう!」というイズムが流れているように感じたからです。こういうことをやってみたら面白いじゃないかと思うことを自分でやってしまう。「遠近に」を聴いて、そんなことを感じながら、長年演奏家として演奏を重ねてきた北村さんが「面白がってやってみたこと」が、とても素晴らしく、そして想像を超える作品だったことに僕はとても感動しているのです。何度も何度も聴いた「遠近に」は、北村さんが日本のジャッキー・ミットゥではなくて、世界のエマーソン北村だな、と教えてくれました。最高です。
再び北村です。なぜ僕がこのようにしてついた「エマーソン北村」という名前のままで来たか、実は自分でも上手く説明ができません。でも例えば曲を一曲作るとして、自分が想定した通りの音を全部入れれば良いかというとそうでもないですよね。自分の意図と違う方向に行く場合もある。その時「これは僕の意図じゃない」と主張するか「とりあえず流れにまかせてみるか」と思うか、僕は、本当により「頑固」なのは「後者」のタイプなのではないかと思うのです。そんなことを今考えてみました。繰り返し、藤川さんありがとうございました。
2014.08.05 Tue
コメンタリー:7. The Call-Up
このコメンタリーは2曲目から始まって、その後はアルバムの曲順通りに書いている。そして、ここでカバー曲が登場することになる!
イギリスのロッカー、イアン・デューリーがブロックヘッズに先だってやっていたバンド、キルバーン・アンド・ザ・ハイローズが1974年に録音したアルバム「Handsome」から。後のパンクやパブロックにつながるロックンロールなのにレゲエやカリプソ、’50年代のポップスやムードミュージックがふんだんに取り込まれていて、要は、もし北村が歌を歌えたらこういう音楽をやりたいと思わせる、ど真ん中のアルバムだ。イアン・デューリーの音楽が素晴らしいところはパーティー音楽であることを外さないのに、歌はどこか寂しげだったりするところ、言い換えれば、言葉に非常な重きを置いているのに言葉だけでは成り立たず、バンドのビートがあってはじめて伝わる言葉を書いていることだ。江戸アケミさんの the most favorite ヴォーカリストだったりもする(余計なことだが、JAGATARA のファンならばこういうところを押さえて欲しいのだ)。The Call-Up という題名も中心的な意味は「徴兵」だと思うが曲中ではいろんな意味が重なっていて英語と日本語を一対一では訳し切れない歌詞になっており、それがカリプソディスコに乗ってサックスが炸裂し、パンが受け、コーラスがまとめる、などなどなど、ああ素晴らしい。The Call-Up という題名自体は The Clash にもあったけど別曲ね。
北村のヴァージョンは素直に、そのオルガンヴァージョンをやったということ。このアルバム制作のかなり早い段階で、当時神楽坂にあったシアターイワトを使わせていただいて、オルガンをダビングした。オルガンは日本製のハモンド X-3。ハモンドオルガンのハードに関するオーソリティである山本力さんに長年面倒を見てもらっている楽器で、この曲ではなぜか予想以上に音が抜けたな。
トラックの方針は、16ビートとか知らないドラマーがパンパンに張ったスネアを叩くサウンドと、BOSS DR-110 という’80年代リズムマシンのサウンドの合体。イントロのキックがフェーダーで持ち上げられるというのはオリジナルへのオマージュで、マスタリングの際 M’s Disk の滝瀬さんにわがまま言って、やってもらった。
2014.08.02 Sat
コメンタリー : 6. トロント・ロック
カナダのトロントは’70年代の一時期にニューヨークに渡って活動していたジャマイカのミュージシャンらが ベトナム戦争に徴兵されるのを避けるために再移動していた街だ、という話をかつての「RM」誌で読んだことがある。ジャッキー・ミットーにもそこで録った「Reggae Magic」というアルバムがある。ただしこの曲はそのタイプの音を目指したわけではなく、時代感でいうなら’90年代の打ち込みレゲエ。
ニューヨークでもロンドンでも、ジャマイカから渡った彼等のスタジオは、台所に機材を並べたような文字通りの「宅録」スタジオ。しかしそこは僕らがいう「宅録」とは違って、自分達がその社会に打って出て行くための大事な足がかり。チープな機材(だと彼らは思ってないし)の打ち込みにどんな気持ちを込めていたのか。
ジャマイカ – トロント間にはまったく及ばないが、僕も子供のころは北海道と関西を頻繁に行き来していた。どこにいても「ルーツはここじゃないどこかにある」という感触が常にうっすらとある。そのせいではないと思うのだけど、「音楽に国境はない!」と声高に訴える音楽よりも、「国境は、ある。しかし否応なくそれに翻弄されてるうち、いつの間にか境界をこえて、こんな風になっちゃった」という音楽の方に、はるかに美しさを感じる。
シュガー・マイノットの打ち込みアルバムの裏ジャケに、やはりチープなスタジオで白人ミュージシャン(明らかに眼がいってる)とニッコニコで写っている写真があって、その感じが一番近い。
この曲には非レゲエネタもありますよ。上がったり下がったりするフレーズにハーモニーがつくことが好きで、その元はファッツ・ウォーラーの「Jitterbug Waltz」。またちゃんとカバーしたいな。