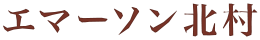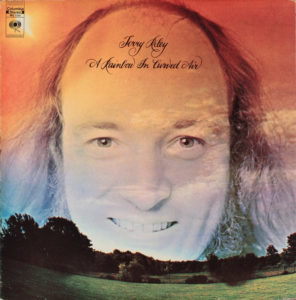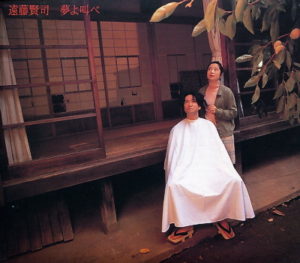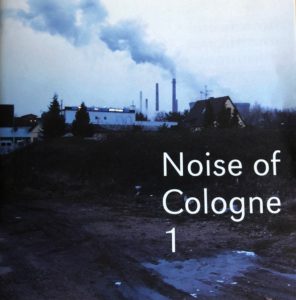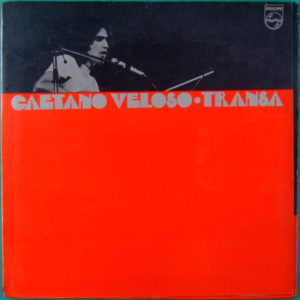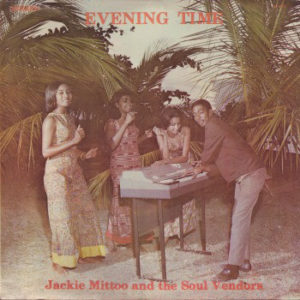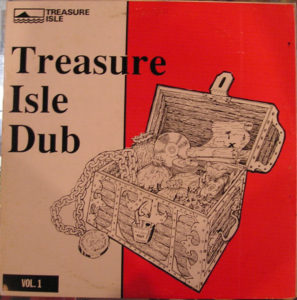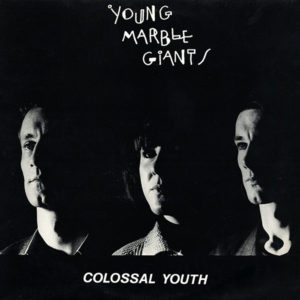エマーソン北村の個人レーベル bubblingnotes の物販サイトを BASE に開設しました。レーベルの作品はもちろん、他レーベルからリリースされた北村関連の音源やグッズも、可能なものは取り扱っていこうと思います。よろしくお願いします!
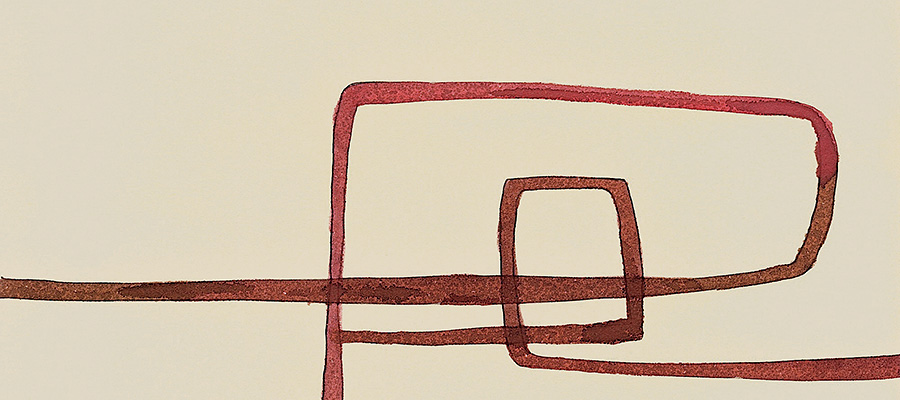
Emerson Kitamura
Column
2020.12.21 Mon
エマーソン北村の 販売サイトを BASE に作りました。
2020.06.15 Mon
CHASING GIANTS エマーソン北村によるセルフレビュー (目次)
2019年11月29日に発売された mmm with エマーソン北村のアルバム CHASING GIANTS についての、僕・エマーソン北村によるセルフレビューです。アルバムの曲順通りに10曲分が、10回のコラムになっています。番号の次が曲名、その隣はサブタイトルです。

(1) introduction -伸び縮みする時間-
(2) Chasing Giants -ただ数えること-
(3) 街のあいだ -欠けたもののこと-
(4) ぼくのともだち -しょうもないけど愛してる-
(5) 見えないゴール -繰り返しと逸れること-
(6) 夏至 -You Don’t Know Me At All-
(7) Astronomer -高速道路の天文学者-
(8) クローサー -ソクチョのつばめ-
(9) 宇宙人
(10) Moon River -世界を見に-

アルバムのリリースインフォメーションはこちら。
試聴、ダウンロード購入のできる bandcamp ページはこちら。
グッズや、自主レーベル作品の通販はこちら。


2020.06.14 Sun
CHASING GIANTS セルフレビュー (10) Moon River -世界を見に-
mmmと僕がはじめて一緒に音を出した2016年の旧グッゲンハイム邸「初夏のセンバツ」で演奏したのが、オリジナルのI’d Rather Beとこの曲、Moon Riverだった。もちろん有名映画劇中歌のカヴァー。

mmmの歌は特に、rainbow’s endというところがいい。本当に、虹が地面に着地しようとする場所で、誰かが待っているような情景が目に浮かぶ。普段英語を話す人によるカヴァーでもあまりそんな風に聴こえたことがないので、ライブ後にそのことを話すと、mmmの方でも歌い方についていろいろ考えている点があるようで、あ、この人はふんわりしているようで、それだけの人ではないのだなと思った。片手ではずっとウイスキーグラスをカラカラいわせていたが。

僕の方はそれに対して、このようなスタンダードでは100回やったら100通りのバッキングができると思っているので、イントロ以外はあえて何も決めずに演奏した。茅場町の七針で、キーボードも外部スピーカーから鳴らし、歌とアンビエントマイクだけで録っている。

意識してやったわけではないのだが、マスタリングの前にミックスの終わった曲をアルバムの順番通りに聴いてみたら、「宇宙人」で何億何万何千何百光年を旅した「僕」が、最後に降り立った惑星で聴こえてきたのがこの曲だった、というストーリーが浮かんできた。mmmも同じだと言う。アルバム作りというのは受け手に曲をできるだけ「聴かせる」作業の連続だから、最後くらいは我々にとっても「聴こえてくる」ようなトラックがあってもいいのではないかと思った。それでマスタリングでは、音量調節などの「聴かせる」作業は何もせず、「宇宙人」からの曲間も非常にゆっくりなものにした(あえてそれ風の音質にすることもしなかった)。「僕」が降り立った惑星がどんなところかは分かったが、結局「彼女」に会うことができたのかどうかは、わからない。

この曲の後は、一曲目に戻って虹の向こうに再び巨人を追ってもいいし、音楽を聴くのを終えて、「世界を見に」出かけてもいい。

* * *

10曲分10回に渡って続いたCHASING GIANTSセルフレビュー、読んでくれてありがとうございました。
本編に書ききれなかったこととしては、まずアルバムのカヴァーデザイン。ルドンの絵とタイトル文字を組み合わせ、アルバムにふさわしい色合いにしてくれたKuidoさん。本当はトレーシングペーパーのレイヤーがもう一層多くて、パッケージを開けるごとにまさに巨人を追っているようなカヴァーになる予定だったのですが、予算の問題で叶わず、申し訳なく思ってます。mmm staffさんによるbandcampのQRコードカード、Masami AokiさんによるTシャツなど、本盤以外でも良いデザインに恵まれている当プロジェクトです。

オフィシャルMVというものは作れてないのですが、2020年2月2日に行われたリリースライブでの、mmm+エマーソン+菅沼雄太+icchieによる動画が、最近公開されました!今のところはChasing Giants一曲だけですが、この後他の曲も、順次公開していきたいと思ってます。

カセットに収録されているのにアルバムには収録されていない「新しい朝」という曲は、曲自体が良くなかったのではなく、カセット音源のアレンジの方向性がどうもこのアルバムの中で収まりが悪かったために、収録を見送りました。アレンジを変えてまたやってみたいです。同じくアルバムの流れがぼやけるという理由から、レコーディングは行ったのにアルバムに収録しなかった曲が、一曲だけあります。楽曲のアレンジ同様アルバムをまとめる上でも、CHASING GIANTSは極力余分なものを残さない方向で作りました。非常にオーソドックスな「アルバム」というものの考え方に立っていると思います。

mmmと僕・エマーソン北村によるこのアルバム以降の作品として、実はすでに一曲、レコーディングの完了しているトラックがあります。他アーティストに提供しているものなので、発表は先方から行われるのをお待ちください。しかし、mmmの歌詞とヴォーカルパフォーマンスも、僕のアレンジと演奏も、これまた一筋縄ではいかない、そしてパワーに満ちたものになっていると思います。どうぞご期待ください!

このセルフレビューはCovid-19によるStay Home期間中に、なかなか二人揃っての活動ができない中で書いたものです。たまたま僕はこのような大量の文章を書きましたが、mmmにとってもきっと同じだけ、違う視点からCHASING GIANTSについて語れることがあると思います。それを聞くのも絶対面白いことだと思うのですが、多分彼女は文章を書くよりも音楽作りそのもので「次」を表現してゆく人だと思うので、僕もそれを楽しみにしながら、また活動のできる状況になったら、一緒にやっていきたいと思っています。みなさんどうぞお元気で!

2020.06.14 Sun
CHASING GIANTS セルフレビュー (9) 宇宙人
アルバムの中でも特に大切な曲。録音した日のことを思い出しながら聴くと今でも9分間分の体力を消耗した気になるが、今の生活の中で自分のよりどころが分からなくなる時、まっ先に聴きたくなる曲でもある。

mmmが十代の時に初めて作ったというこの曲はまず何よりも、彼女自身に向けて書かれている。この曲を書き、歌うことで、まず自分が救われる。そして同時に、自分のことを全く知らない誰かが、この曲に書かれていることを自分のことのように感じ、救われる可能性がある。それはポップソングそのものの本質でもあるし、音楽作りで一番大事にしたいことでもある。

この曲はすでにmmmのファーストアルバム「パヌー」で一度リリースされている。それなのに僕がこの曲をアレンジして再びCHASING GIANTSに収録したいと思ったのは、「パヌー」のヴァージョンに不満があったからではなく、この曲で歌われているストーリーはmmmの曲の中でも特に普遍性があると思ったからだ。完全なストレンジャーを好きになってしまったことで味わう、何億何万何千何百光年の孤独。ライブ慣れするより前の時代に作られた曲だから、今のmmmにとっては若干キーが高すぎた。しかし、楽に歌えるキーまで下げると何かが違ってしまうので、結局元のキーのままでいくことにした。

歌い手と共演者の関係がごまかせないものになるのは、こういう大事な曲を一緒に演奏する時だ。僕はmmmの歌をどう聴いているのか、mmmは僕の演奏に何を求めているのか。人間的な関係ももちろんだが、それ以上に自分の音楽観や人前で演奏することをどうとらえているかが、否応なく明らかになるし、またそういう演奏にならなければ意味がない。

mmmの弾き語りを観たことのある人なら、この曲の魅力は自由なタイミングで伸び縮みする、演奏の「揺れ」にあるとすぐに思うだろう。僕が加わる場合も、この演奏に「自由に」ついていくだけで、十分良いものになると思われた。でも、と僕は思った。それで本当に、この曲の持つ大きな時間の流れを表現しきれるだろうか?歌い手に合わせるだけの演奏というのは、その時はいい感じでも、すぐに歌い手に「おんぶ」するだけの演奏になってしまう。そうなると曲の伝わり方は平面的になってしまい、二人の演奏はいつまでたっても完成形が見えてこない。どうしたらいいだろうか?

歌い手と共演者の関係を考える時、僕がいつも頼りにする動画がある。クラシックブルースシンガー、ベッシー・スミスとピアニスト、ジェイムズ・P・ジョンソンによるデュオ演奏。宇宙人からかけ離れていると思われるかも知れないが、僕にとって音楽は常に、例えば「シンセを手に入れたジェイムズ・P・ジョンソン」を想像するようなことなのだ。
Backwater Blues / Bessie Smith (vocal); James P. Johnson (piano) 1927

もうひとつの大事な準備は、メロディをコードや小節の枠から一旦はずして、「1拍ごとに把握する」ことだった。mmmのメロディを最初から最後まで、休符を含めて言葉と一緒に譜面に書き出してみるのだ。そうしたら、自由なタイミングで揺れながら歌っているように聴こえるmmmのメロディが、実はかなりかっちりした時間軸の上にできていることが分かった。そして、必要なものといらないものが見えてきた。コード進行もほとんどいらない、打楽器もいらない。いるものはただ、ほぼ一種類のループだけということになった。ただしそのループは、mmmの自由なタイミングを縛るものであってはならない。ループ音楽で僕が思い出すのは、例えば高校生の時に友人から教えてもらった、こんなものだ。
A Rainbow in Curved Air / Terry Riley 1969

こうして「ブルースのように揺れながら、テリー・ライリーのように繰り返す」という僕の演奏方針ができた。タイミングの「読み」を求められる、難しい課題だ。mmmには、僕がいてもいなくても同じように、自由に演奏してほしい(これもmmm with エマーソンの演奏において常に言っていること)。だから録音はクリック(一定のテンポを刻む、メトロノームのようなもの)を使わない、9分間の一発勝負である。二人のタイム感をつなぐ上では、mmmの弾くエレキギターが役に立った。ポローンと弾いているだけに聴こえるこのギターも、歌の合いの手として、曲の流れをとてもよく表現している。オルガンは長年使っているヤマハのYC-10、足鍵盤でシンセベースと、アルペジエーターやノイズ以外はライブで演奏している。

実は、録音当日に「OK」とされたテイクは、今アルバムで聴けるテイクではなかった。アルバムで採用されているテイク(テイク1)は録音した日には、ほんのちょっと思った通りにできなかったとか、声がかすれたという理由で、僕も含めた二人の「演奏記録」から除外されていた。それがたまたま他の作業が「押し」たせいでミックスまで1ヶ月近く時間が空き、録音当日の記憶もすっかり薄れたころ(その日は真夏の暑い日だったし)、再び録音ファイルを開いてこのテイクを「発見」したのだった。冒頭の「僕は今日…」を聴いた時からすでに、僕はこのテイクの演奏に引き込まれていた。新鮮というのとはちょっと違う、音楽をやる「覚悟」のようなものが、他の「上手な」テイクとは断然ちがうのだ。mmmにそのことを話して、改めて聴いてもらったところ、彼女も同意見だった。それでこのテイクを採用して、ミックスをして、今みなさんに聴いてもらっているような宇宙人ができあがった。

演奏者の「覚悟」というのは、以前はよく言われたことだ。いかなる時でも音楽の受け手に対して「前を向く」姿勢、とでも言えるだろうか。mmmに限らずこの数年間、いろんな世代のアーティストとライブをしていて、この人の「覚悟」はまだまだだなあと思うことは、正直、ある。しかし同時に、「覚悟」の中身が90年代や00年代とはすっかり変わってきていることも、また感じる。音楽をとりまく状況の変化を考えれば、当然のことだと思う。だけどこの曲を、二人の「覚悟」を込めた形でまとめられたことは、きっと後で生きてくるのではないかと思っている。

この先さらに、我々の「覚悟」をめぐる状況は、どう変わっていくのだろうか。mmmの世代のミュージシャン達は、その中をどう生きていくのだろうか。mmmとの録音作業が終わって彼女が帰った後に頭に浮かぶことは、いつもそんなことだった。

宇宙人の歌詞を追っていると、いつもあることが疑問になる。結局「僕」は、宇宙人である「彼女」を見つけられたのだろうか。「僕」が光速でブラックホールに吸い込まれてゆくような間奏の後で、新しい歌詞はないまま、曲は終わる。「締め」のないのはmmmの曲の特徴だが、芸術的にはなくてもいいと思う反面、素直に気にもなる。
さて、その結果は…?

(追記)
ひととおりこの原稿を書いた後でふと思い出し、どうしても頭から離れないので書いておきます。
僕の中で最もこの曲につながっているアーティストは、ベッシー・スミスでもテリー・ライリーでもなく、遠藤賢司さんかも知れないと、今気がつきました!もちろんmmmの音楽上のテイストとは異なりますが…
エレキギター一本の弾き語りというスタイル、「宇宙」というキーワード、長尺の曲、そして何より「覚悟」ということを言葉でなく姿勢で感じさせてくださったのは、エンケンさんの演奏だったと思います。ありがとうございました。

Backwater Blues / Bessie Smith (vocal); James P. Johnson (piano) 1927

2020.06.13 Sat
CHASING GIANTS セルフレビュー (8) クローサー -ソクチョのつばめ-
カセットのために2018年に録音された、アルバムの中でもかなり古い曲。もともとはエマソロの曲として、というかインストにも歌の曲にもなるようにと思って僕が作った曲で、mmmとだけでなくソロライブでも演奏している。

サビの、メジャーとマイナーのコードが繋がっている部分のように、明るいとも暗いともつかない、灰色の情景が浮かんでいた。それを転調を繰り返すメロとコードにまとめて(僕はいつも、もっとシンプルにしたいと思っているのだが)、歌詞を書いてほしいとmmmに渡した。歌詞は一発でOKになって、その時から曲名は「クローサー」になったが、レコーディング時には「灰色」と呼んでいた。

この時点では、二人ともmmm with エマーソンがこの先アルバムを作ったりヨーロッパツアーをするようになるとは思っていなくて、この曲もとりあえず一曲完成させよう、という感じだったから、mmmにとってこの曲の歌詞はどちらかというと僕に「頼まれて作った」側面が強かったのではないかと思う。しかし、mmmに限ったことではないが、仕事というのは往々にして、立候補して意識的に「自分を表現」したものよりも、人に「頼まれたからやっただけ」のものの方が、素晴らしい結果を生むことがある。この曲もいい例で、単語の響きと流れの良さ、あえて古いポップソングのような情景のつづり方など、mmmの歌詞の中でもかなりの美しさを誇るものだと思う。

この歌詞をもらって間もない2018年の5月に僕は、韓国・ソクチョのフェスでソロライブをした。ソクチョは韓国の東海岸にあり、トンヘ=日本海をはさんで向こう側は富山や舞鶴だ。北朝鮮にも近く、朝鮮戦争時には北から避難してきた人も多かったと聞く。そんなソクチョの海岸でリハをしていたら、ツバメが飛んでいた。このツバメはどこから来たのだろう、はるか遠くから来たのかもしれないと思ったら、不意にこの曲の「私はツバメ、homeに導かれてゆく」という言葉が浮かんできた(例によって想像訳)。五月。homeとは家のことか故郷のことか。何ていう符合だろうと思いながら、海と空を眺めた。

その他にもこの曲には符合が多い。フェスでは「壊れたおもちゃを10セントで売っている」ようなフリーマーケットもやっていた。レスリーはかかってなかったけど。レスリー・ゴーアは1960年代から活動したUSのシンガーで、十代からポップスターとして人気を得、2000年代以降は自身の体験にもとづいたLGBTに関する発言でも広く知られた人だ(僕はシンガーとしての彼女しか知らなくて、この歌詞をもらうことで改めてその発言を知ることができた)。

インストにも歌の曲にもなる曲だが、僕が演奏する内容はソロの時もmmmと演奏する時も変わらない。僕は常にメロディを弾いているから、mmm with エマーソンの時は二人ともメロディを担当することになる。二人しかいないのにメロディ二本というのはなんだか非効率だが、「歌のバックの時は伴奏に徹します」というスマートなやり方に僕はどうも違和感があって、mmmが歌っていてもメロディを弾くのが、何というかこの曲に対する礼儀のような気がしている。

小さな音だがしっかりサンバのリズムを刻んでいるのは、PO-12というスピーカ内臓のドラムボックスを、ウチの洗面所で録ったもの。sakanaの水というアルバムに入っているレインコートという曲の、時計の音に似ているなと後から気がついた。


2020.06.13 Sat
CHASING GIANTS セルフレビュー (7) Astronomer -高速道路の天文学者-
mmmのソロには、ギターで弾き語りをするスタイルの他に、シンセを使ったエレクトロニックなライブもある。これがなかなか良くて、mmm with エマーソンでもその要素を生かして何かできないかなと思っていた。Astronomerを録音したのはレコーディングも押し詰まった頃で、このスタイルでのやり方にはまだまだ改良の余地があったかもしれないが、僕が勝手に「B面」と考えているこのアルバムの「夏至」以降の流れにおいて、この曲は大事な位置を占めている。

東京のバンドが大阪でライブをして宿泊せずに東京に戻る「夜走り」の行程をとる場合、車が大阪を出て京都を過ぎ、滋賀県と三重県の県境あたりに来るころ、不思議な時間が訪れる。ライブと打ち上げで浮かれた気持ちは次第に静まり、窓の外の暗闇はどんどん深くなって、星の数が増えてゆく。そんな(運転手以外は)ちょっと非現実的な時間にひたっていると、現れるのだ、巨人が。山あいに、暗くて大きな一つ目がこちらを見ている。というのはもちろん錯覚で、その正体は巨大な送電線の鉄塔なのだが、現れる角度と点滅する照明が、ちょうどCHASING GIANTSのカヴァーに使ったルドンの絵にそっくりなのだ。

その日僕とライブを終えたあるアーティストも、この抽象的な時間に引き込まれているようだった。ただし彼女の場合は大阪で飲んだアルコールの量が半端なかったらしく、三重県に入ってもゴキゲンな勢いは全く衰えなかった。巨人どころか彼女の頭には銀河がひろがっているらしく、体をぐらぐらさせながら窓の外を眺めては、「うわーなにこれー星いっぱーい!キレイー!」と叫び続け、それは車が名古屋の手前にさしかかるまで何時間も続いた。その時思いついたのが「酔っ払いの天文学者」という言葉だった。ジェフ・マルダーが僕の好きな1920年代のトランペッター、ビックス・バイダーベックの曲をカヴァーしたアルバムがあって、そのタイトルがPrivate Astronomyというのをどこかで覚えていたのだと思う。

その次にmmm with エマーソンで大阪に行ったのは、フリースペース&CDショップHOPKENの閉店イベントだった。エマーソンもmmmもお店の初期からお世話になった、ポリシーのある素晴らしいスペース。閉店イベント自体もすばらしいもので(記録はこちら)、たくさんのアーティストがいい演奏をした。ライブが終わってお店が閉まってもホテルに戻る気がしなかったので、ライブで会った電子音楽家YPYやその周りの人々と、夜中の大阪の街をぶらっと遊んだ。コンビニの駐車場から通りの向こうを眺めると、ここにも巨人が隠れていそうな暗闇があった。西成だ。深夜までいろいろな話をしてホテルに戻ると夜が明けかけていて、空は青とも赤ともつかない、見たことのない色をしていた。ちょうど今から一年前、2019年6月のことだ。

さらに話は飛ぶ。昨年10月にライブで訪れたケルンで、現地のレコード店a-musikをやっているフランクさんからNoise of Cologneという、同地での実験音楽や電子音楽の歴史をたぐるコンピレーションCDをいただいた。内容も良かったが、カヴァーに使われている、我々のイメージするケルンとはまた違った日常そのままの「退屈」な風景を切り取った写真も印象に残った。ライナーノーツもどこか「俺らの街」を拠りどころにしているようで、本来は地理や歴史の括りから自由になるために生まれた実験音楽や電子音楽が、ケルンでも大阪でもこんな風にローカルに存在していることに、僕もなんだか愛着のようなものを感じた。

Astronomerについてはもうひとつ、プロデュースとミックスがmmmだということを強調しておきたい。僕のリーディングのディレクションも彼女が担当している。「普通に話しているままの声でやるように」と言われたので、エマソロでのこのタイプの曲よりも、僕の声は柔らかく録れている。ミックスも、アナログミキサーの基本をざっと説明したら、30分後にはもう使えていた。mmmにはたくさんアナログ卓を使って作品を作ってほしい。


2020.06.12 Fri
CHASING GIANTS セルフレビュー (6) 夏至 -You Don’t Know Me At All-
海外で評価され、ヨーロッパツアーのきっかけともなったRock Your Babyに次ぐ「グルーヴもの」の新曲。しかし単なる「次」ではなく、Rock Your Babyよりもはるかに込み入って、それぞれの「妄想」が十分に現れる曲になった。そのわけのひとつにはmmmの歌詞、もうひとつには僕の、レゲエを要素として音楽を作る上でのこだわりがある。

レゲエでは、トラックが歌から独立していて、ひとつのトラックにいろんな歌が乗るのは普通のことだ。レゲエ(というか、その元となった1960年代末のジャマイカ音楽ロックステディ)を少し聴いたことのある人なら、この曲のトラックがいつのどの曲に影響を受けているかを簡単に言い当てることができるだろう。それはそれで面白いことだが、僕のこだわりはそういった「音楽スタイル上の正しさ」にはない。普通は「別々」のものである歌とトラックが、一緒になってできあがるような曲にすること、そして、ロックステディから逸脱しながら、ちゃんとそこに戻ってくる曲にすることが、僕の目標だった。それはロックステディという音楽自体が、始めからそういうものだからだ。

以前から僕は、カエターノ・ヴェローゾのアルバムTransaに入っているNine Out of Tenという曲の雰囲気で何か作れないかと思っていた。カエターノのロンドン亡命中に作られ、「ポートベローを歩いていたら、レゲエが聴こえてきた」と英語で歌われる曲(例によって訳は対訳ではなく北村の想像訳)。その心情は一曲前のYou Don’t Know Meという曲のタイトルにも表れていて、曲そのものはレゲエでないことがまた良かった(イントロで一瞬だけレゲエでも演奏されている。この部分のコード進行は「夏至」のサビに影響を与えている)。そんなことを思いながら、この曲が作られた1970年代初頭に聴こえるレゲエと言えばルーツレゲエではなくロックステディ、ロックステディと言えばジャッキー・ミットゥーのDrum Song、という連想で「夏至」のベースラインができていった。(正確にはDrum Songは1968年で、カエターノが聴いたであろう初期レゲエよりも少し古い。時代考証を何より大事にする方には申し訳ないけど、僕はあくまで音で思考しているのでその辺は意外といい加減だ。)

ベースラインが見えたところで次に、メロディや構成は、他の共作曲とは違って二人でジャムしながら作りたいと思った。例えば街のあいだのような曲は、各々が相手の提案をファイルで受け取ってから、一人でアイデアを重ねるという方法で作られた。実は僕は、バンドで延々ジャムしながら曲を作るのは、あまり好きでない。よっぽど気心の知れたバンドならともかく、「グルーヴに委ねて」と言いながら実は相手の出方をうかがっているだけという「ジャム」の多さに、ちょっと飽きているのだ。ファイルのやりとりの方が、リアルよりももっと相手との距離を縮められる場合の方が実は多い。しかしこの曲では、歌がなく、ソロもなく、ただ「グルーヴに委ねて」いるだけの時間を作りたいと思ったのだ。

ジャムすることで予想通り?曲はどんどん普通のロックステディから逸脱していった。キーは短3度で上がったり下がったり、リズムはスローファンキーとワンドロップを行ったりきたり。極め付けは我々が「心中」と呼んでいたパートで、ここは何だろう、ニューウエーブ?しかしこのパートのおかげで曲は意味あるものになった。それを支えているのは、mmmの歌詞だ。

歌詞を書いてもらう前に、僕は彼女にこんな話をした。僕はレゲエが好きだけど、古いレゲエに多い、マッチョで男性優位的な内容の歌詞にはついていけない。歌詞だけはレゲエにはないものにしてほしい。そうしたら彼女は、まさかの幽霊譚、同時にラブソングでもあるような幽霊譚を書いてきた。どうも彼女は、僕のひねったリクエストに対しては、さらにもうひとひねり加えて返してやろうと狙っているようだ。そんなあまのじゃくは、大歓迎だ。

演奏上の特徴はもちろん菅沼雄太(すがちゃん)の参加、そして何と言ってもmmmのベースとフルートだ。mmmはもちろんレゲエベースは初めてと言っていたが、むしろ中途半端に「レゲエベースとは」などど考えていない演奏が、良いグルーヴをもたらしている。だってジャマイカのミュージシャンは「レゲエっぽくベースを弾こう」とは言わないでしょう?ただ良いベースを弾きたいと思って演奏する、それと一緒なのだ。すがちゃんは口径のとても大きなバスドラムを持ってきた。それがさほどローエンドのないもので、良かった。大きなバスドラムは低音がたくさん出るというのも、レゲエはローエンドを強調するということも、実は間違った常識。

ミックス上の特徴は、この曲ではダブっぽい要素もあるのに、ディレイをほとんど使っていないことだと思う(「心中」パートでは使っている)。mmmのフルート、すがちゃん、そしてエマーソンと、人間の側ですでに「ダブ」ができていると思ったからでもあるし、僕が最も好きなダブアルバムTreasure Isle Dubの、ほとんどディレイが使われていないミックスも念頭にあったからだ。

ロックステディの話に戻る。ロックステディを担ったミュージシャン達はこの時期に、驚くほど幅広い音楽を取り入れている。インプレッションズをはじめとするUSのコーラスグループはもちろんのこと、モータウン、ファンキー、オルガンジャズ、はてはイージーリスニングやエキゾチカといった「白人音楽」まで。僕がレゲエ、特にロックステディを好きで良かったと思うことのひとつは「レゲエの中にすべての音楽が入っているし、すべての音楽の中にレゲエが入っている」と感じられることなのだが、その理由は、自分たちだけのものである太いグルーヴ(ベースライン、3拍目の重要さ、コピペでは作れないループ感など)は、外からの要素が加わってもまったく薄れることがないからだ。ロックステディに影響を受けて音楽をやるということは「それっぽく」演奏することではなく、はずせない部分は押さえながらも、進んで逸脱して、形式ではないその曲の持つストーリーに常に戻ってくることだと思っている。

この曲のストーリーは、「月に透けている、嫁に行ったはずの娘」に集約されている。彼女の中には、カエターノが1972年に「お前らみんな、俺のことなんかぜんぜん知らないだろ」と歌った気持ちに通じる「見えていない寂しさ」が流れている。

ロックステディは本当に不思議な音楽で、それが制作されたのはスカとレゲエの間に位置する、1966年から69年くらいまでの、たった3年ほどの間だ。その間に作られたレコードを、30年や40年かけて集め、聴く人が大勢いる。音楽の流れにおける時間の不均等さ、「伸び縮み」はこんなところにも現れている。


2020.06.05 Fri
CHASING GIANTS セルフレビュー (5) 見えないゴール -繰り返しと逸れること-
2018年
04月22日 街のあいだ
06月14日 クローサー
06月16日 見えないゴール
2019年
06月05日 Week-End Fes ジングル (introduction)
07月09日 僕のともだち
08月05日 夏至
08月06日 Chasing Giants
08月14日 宇宙人
09月16日 moon river
09月20日 Astronomer

今調べたら、CHASING GIANTS収録曲の録音開始日はこのようだった。これはパソコンのファイルを作った日だから(僕はアナログのレコーディング卓で作業をしているが、音自体はパソコンに録っている)、実際に曲作りを始めたのはもちろんこれよりも前だ。

見えないゴールはmmmの2017年当時の新曲で、唯一レコーディングの前からライブでやり続けていたオリジナル曲である。他の曲は(もちろんリハーサルはしているが)レコーディングで初めて完成形を演奏するか、ひな形をライブで数回やったくらいで録音日を迎えた場合が多い。ポップ音楽のレコーディングとしては普通だと思うが、ミュージシャンとしては、新曲は何度もライブでやって上手になってから録りたいものだ。僕も演奏家としてはその気持ちはよくわかるが、それが必ずしもベストだとは思っていない。
アーティストにとって、自分がイメージしたものを「一度聴いてしまう」効果はとても大きい。それまで頭の中だけで鳴っていたものを一度現実の演奏として聴いてしまうと、二度と同じ様にはイメージを働かせることができなくなってしまう。「ライブでこなれる」ことには、良い意味も悪い意味もあるのだ。

だから、録音時には既に「でき上がっていた」この曲、見えないゴールをアルバムの他の曲と並べて聴いた時には、ちょっと収まりの悪さを感じていた。レコーディング末期の、お互いが自分をさらけ出してアイデアをふり絞っているような演奏とは違い、どこか「mmm with エマーソンって、こんなものかな」とわざわざ設定した姿に向かって演奏しているような雰囲気がある。
…と、アルバムをまとめた頃には、思っていた。しかし、今聴いてみると、どうして歌も演奏も素晴らしい。特に声には、作業が連続した時期とはまた違った伸びがある。僕についても同様で、足鍵盤を使うというアイデアの自由さとそのグルーヴ感は、2019年には出せなかったかもしれない。

曲自体も今聴くと、新しい姿が見えてくる。「見えないゴール」というキーワード自体がたまたま2020年の現実とリンクしてしまうのもあるが(ちなみにこれは、仮タイトルがそのまま正式な題名に昇格したとのこと)、歌詞の内容はそれ以上に繊細で、視覚的で、見方次第ではロマンチックだ(指の下では小人 誰かが残したダンス)。

曲の構成も一見シンプルに思えて実は不思議だ。最初から別のコード進行に向かったり、頭に戻って同じ展開が繰り返されるかと思いきや間奏になったり。特に、これまた「締め」のないまま「出る」という言葉を4回繰り返して終わるアウトロは、まるで自分の思い通りに時間が進まないSF映画みたいだ。何度も繰り返されるコードの中でベースだけが同じ音に行くのを避け、不自然なほど高い音程に到達してしまう。

繰り返すことと、逸れてしまえばもはやそれまで(必ずしも悪くない)、という両方を意識することは曲作りや演奏の本質でもあると思うし、同時に、ライブやレコーディングといったミュージシャンのプロジェクトの進め方を考える時にも、大事な要素であると思う。

* * *

ここまで読んでくれてありがとうございます。もしCHASING GIANTSがアナログ盤だったとしたら、今ここは、針がレコード中央の溝を終わりなくループしているところ、A面の終わりです。残り5曲についてもできるだけ早く、更新してゆきたいと思います。

2020.06.05 Fri
CHASING GIANTS セルフレビュー (4) ぼくのともだち -しょうもないけど愛してる-
「しょうもないけど愛してる」という言葉が示している通りの、愛すべきトラック。聴いてくれる方からの人気も高い。録音もミックスも、比較的悩まずに進んだ。もちろん、それだけではない部分もあるのだが。

mmmの「小さなともだち」を歌った歌詞は、簡単だがうなずけるストーリーと、視覚的ではっとする言葉が、多すぎることなく並んでいる。特にこの「愛してる」という言葉はmmmの作詞の特徴をよく表してると思う。
ご存知の通りmmmは、英語と日本語の両方で歌詞を書く。「愛してる」という単語は、日本語だけで歌詞を書く人にとってはなかなか上手に使えない言葉だと思う。それをさらっと出せるmmmはやはり英語を話す人だと思うのだが、本当に良いと感じるのは、それが聴く人に、日本語としてとても自然に入ってくることだ。歌詞カードを見ずに曲を聴いた時、この部分から英語のloveを連想する人は、ほとんどいないのではないかな。少しだけドキッとして、それがなぜかと考えて初めて、そのことに気づく。そんな自然さをこの「愛してる」は持っている。

mmmの告知などをしているスタッフさんともよく話すのだが、これはblueなど、mmmの他の日本語曲を演奏するときにもいつも思うことだ。英語を知らなければ書けない日本語ではあるが、日本語しか知らない人の歌詞よりも日本語らしく響く。よく使われる日本語だけが日本語らしい日本語なのか、という疑問を投げかけるテーマでもあると思う。そして多分逆も言える。mmmの英語詞は、中途半端な英語力しか持たない僕にとっても視覚的にとらえやすく、音で記憶に残りやすい(しかし、その意味をきちんと知ることも大切だ)。それで、僕がmmmの曲をアレンジをする際には、最初は極力歌詞資料を読まないようにしている。そのせいで、細かい表現上の苦労をたくさん見落としているような気もするが。。

歌のレコーディング自体もあまり苦労せずに済んで、ほぼテイク1でOKだった。そういう過程はミックス・マスタリングと作業過程を進めるほど明らかになるもので、この声の柔らかさはレコーディングテクニックで作れるものではない。特に二番の「ノックしたとこで誰にも答えないの」という部分はアルバム中でもベストの声のひとつだと思う(全く別の意味で、もう一つのベストは宇宙人だと思う)。ウィスパーともナチュラルとも違う、mmmの声としか言いようのない声。そして僕はそういう部分には、何も手を加えていない。

改めて聴くと、演奏のグルーヴが「ゆるくてすごい」。ドラムボックスはローランドTR-66という古いものを使い、特殊な方法で内臓のパターンとは違う音数の少ないパターンを演奏させているのだが、まるで人が揺れながら電子ドラムを叩いているようだ。実際にはドラムボックスはとても正確なタイミングを刻んでいる。それが揺れながら二人の演奏についてきているように聴こえるのは、我々の側が自分のリズムで、相手を聞きながら、機械的なフレーズを演奏しているからだ。ミスタッチがあってもそのまま残している。

アレンジ上でのこの曲のハイライトは、間奏での口笛とキーボードのユニゾンと追いかけだろう。これも細部が決まる前にとにかく録音してみたかったから、二人が微妙にずれていてもそのままのテイクを使っている。同じコード進行が二回繰り返されていて妙に長いのだが、その長さは僕にとっては一番と二番の間の、ストーリー上の時間経過を示すものだ。キーボードは人から長く借りているのかいただいたのか分からない、多分1970年代の電子ピアノだ。
そして二番、とても大切な二番が過ぎたあと、ストーリー的にはあまりかちっとした「締め」がないまま、やや唐突に曲は終わる。これもmmmの曲の特徴だと思う。二番で終わるか、そうでなければ三番には行かず、別の風景へと逸脱してしまうことが多い。

この曲は珍しくキレイに終わっているが、そのキレイさはどことなく曲には含まれなかった「逸脱」をイメージさせるところもあり、それがこの曲をハッピーなだけではない独特のテイストを持ったものにしていると思う。このトラックだけでも楽しめるが、ぜひ、アルバムの他のトラックと合わせて聴いていただきたい曲でもある。

2020.06.05 Fri
CHASING GIANTS セルフレビュー (3) 街のあいだ -欠けたもののこと-
この曲ではいろんなものが欠けている。演奏的には楽になっても余分な要素は曲に入れない、という方針はmmm with エマーソンだけでなく僕の関わるものの多くに共通しているが、それは僕が、そもそも音楽というものは、どこか「欠けた」人のためのものだと思っているからかもしれない。

第一の「欠けている」要素は、もちろん歌詞の内容だ。この曲を作った頃は渋谷の街区の取り壊しが多かった時期で、たまたま同じ頃に抜いた親知らずの感覚と、なくなったビルの感触が重なっていた。そんなことを思いながら骨子となるリフと歌詞に関するキーワードをmmmに送ると、メロディのアイデアが返ってきた。そうやってやりとりしながら徐々に、今ある曲の形を作っていった。

第二に、人間味に「欠ける」そのリフのこと。自分で言うのも何だが、多くの人がエマーソンの演奏の特徴として思い浮かべるのは、このリフのような「機械的なフレーズを、機械を使わずに弾く」ことではないだろうか。なぜ手弾きなのか?打ち込みを使わないならもっと「自然な」フレーズを弾けばいいのでは?こんな質問が出るのも当然だと思うが、ひとつには、僕がミュージシャン界に入った1980年代後半には「機械のように正確に」演奏できることが「売れる」ミュージシャンの必要条件だったということがある。僕は当時の「売れてる」音楽はくだらないと思いながらも、何とか「売れ」ようと必死にクリック練習(拍を刻むガイドに合わせて練習すること)をした。その経験が否応なく、自分の演奏には残っている。
今になって思えば、「ジャスト」がもてはやされた1980年代には、自由なタイミング編集が可能になった現在に比べて、正確ということがまだそれほど当たり前ではなかったのかもしれない。当時のMIDI機材の精度に比べれば、1970年代以前のアナログシーケンサーやテープループで作られた音楽の方が、タイミングの正確さでははるかに「本物」である(そして最近復活している)。それらの音楽がポップスの一スタイルに使われるようになる過程で、ラボにこもって数分の一秒のループに何日もかけるようなものから「売れる」ミュージシャンの必須科目へと、作り手の中での「時間」の凝縮のしかたも変化してきた。そんな「タイミング」に対する理想とあやふやさとを、僕の「手」は表していると思う時がある。

ところで僕が当時出会った音楽には、そういった流れとはまったく別の意味で「機械的」な要素を持つものがもう一つあった。レゲエ、サルサ、アフロビート。打楽器であろうがコード楽器や管楽器であろうが、ひとつひとつのフレーズはパターン化され、「機械的」な正確さで繰り返される。しかしそれらが組み合わさって全体を形づくった時、ものすごい揺れと感情が生まれる。しかもそれはポップだった。何より、人力で演奏されている。

ループミュージック、ルーツミュージック、そしてニューウエーブ、これらの音楽にずっと引っ張られながら、しかもどれにも属さない・属せないミュージシャンとして僕は活動してきた。「パターン」とか「ジャスト」といった問題に対して僕の価値観は常に、疑問を投げかけられ続けてきた。僕のタイミングマニアぶりはそんなことで成り立っているのだと思う。だからこの曲のリフのような要素は、「じゃあこの曲にはこれ使おうか」という風に自由に選ぶことのできるものではない。自分について回っているものなのだ。

三つ目に「欠けている」ものは、僕の音楽で大事な要素である「ベース」だ。普段は僕が左手で弾くことの多いベースというか低音パートは、mmmのギターが担当している。歌い手が自分で弾くこういうギターはすごくいい。mmmはベーシストでもあるが、あえてこの曲ではベースでないのがいい。いうまでもなくYoung Marble Giants的でもあるし、アフロビートのテナーギターのようでもある。
ただしライブでは、ベースのないことは音量感のなさにつながる。他の曲と並べると、テンポはあるのに音量がかせげない。だからリハでは何度もベースを加えようと試したのだが、その度に断念した。何かが違うのだ。「欠け」を埋めると別の「欠け」が見つかり、そのすべてを埋めるまで試行錯誤を続け、最終的に、つまらないものになる。これを僕は「ライブ音量症候群」と勝手に呼んでいる。録音や配信では曲ごとにトータルの音量が変えられるが、ライブではその日の最大音量はセットリストの中で一回あるだけだ。だから一つのショウの中でいかに「音量を下げられる」かがライブ演奏の醍醐味なのだが、ライブというものは何度もやっていると、その辺の感覚がまひしてくる。それに抗したくて、今でもレコーディングのままのバランスでこの曲を演奏している。
最近この曲には、mmmが激しいギターソロを弾くパートを加えてみた。これもまた音響的にはアンバランスなものだが、僕は結構、このデュオらしくて気に入っている。

この曲を作った頃にはたくさん欠けていた渋谷の街も、気がつくと随分いろんなものに埋められている。その多くは自分から遠く離れた、見ても冷たい気持ちにしかならないものだ。

逆にとても嬉しかったことは、ライブ物販で会った人に「街のあいだDJでめっちゃかけてます」と言われたことだ。CHASING GIANTSは多くの方にとてもいい聴き方をしていただいていることを、いろんな機会に実感しています。